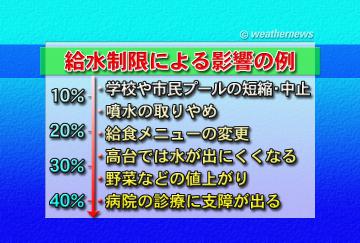8月7日は二十四節気のひとつ、立秋(りっしゅう)です。
暦の上ではこの日から秋になりますが、実際は一年の中で一番気温が高く、暑さの最も厳しいころです。
立秋以降の暑さを「残暑」といい、「暑さ寒さも彼岸まで」というように秋の彼岸の9月半ばごろまでは暑い日が続きます。
しかし、かつては、立秋を過ぎれば、暑い中にも秋の気配を感じられる日が少しずつ増えたものでした。
朝晩のさわやかな空気、千日紅(せんにちこう)やキキョウ、ハスといった花から、暑さのピークを越え、これから秋が近づいてくることに気付かされることもありそうです。
お天気豆知識(2025年08月06日(水))


萩は秋の七草のひとつですが、ハギ(ヤマハギ)の咲きはじめの時期は、はやい所で7月下旬、ほとんどの所は8月中旬から下旬ころです。満開になる時期は、これより2週間から3週間後で、8月下旬から9月下旬ころです。
ハギはマメ科ハギ属の総称ですが、ふつうはヤマハギか、ミヤマハギのことです。ハギは日本の各地に自生しており、また庭園にもよく植えられています。大きさはヤマハギだとおよそ1.2メートル、花の色は紅紫色や、白色のものなどがあり、蝶形をしています。
ハギの花は、古くから、日本の秋の情感を代表していたようで、万葉の歌人も好んでハギをテーマに選びました。「万葉集」には、花の中で最も多い141首で使われています。昔からハギの花は日本に住む人々に愛され、鑑賞されてきたことがわかります。
ハギは鑑賞するだけでなく、その幹を刈り取って茶室の垣などを作るのにも使われていました。さらに、やせた土地でも良く育ち丈夫なため、砂防用としての堤防や、緑化にも利用されてきました。
このようにハギは様々な形で、日本に住む人々と深く接してきたといえます。