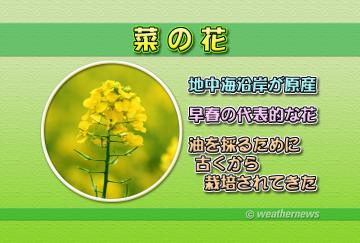ウグイス
どこからともなく聞こえてくるウグイスの声。春の訪れを教えてくれるウグイスは文字どおり春告げ鳥です。ウグイス色といったら皆さんはどのような色を連想しますか。ウグイスパンやウグイス餅などで目にする、抹茶のような、緑といったところでしょうか。しかし、実際のウグイスの羽の色は、茶褐色をしています。色彩学から見ても、本来のウグイス色は苔(こけ)色よりも濃く、どちらかというと緑がかった濃い茶色といえるでしょう。ちなみに、ウグイス色のように鳥が色の名前に用いられるようになったのは、多くが江戸時代になってからといわれています。平安時代の場合は、植物から名前を付けることが多く、また、派手で単純明快な色が好まれる時代でした。ウグイス色のように、地味な中間色の色が好まれるには時間が必要だったのでしょう。