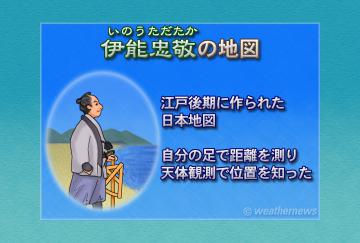10月も半ばを過ぎ、日ごとに秋が深まってきています。これからの季節においしいものと言えば柿でしょう。
柿は生で食べるものと干柿にして食べるものがあり、生で食べる柿は甘柿、干柿用は渋柿を使います。一見違いはなさそうですが、包丁で切ってみると、2つに大きな違いがあることがわかります。
甘柿は果実に黒いはん点がありますが、渋柿にはありません。この黒いはん点こそ、柿が甘いか渋いかを決める「タンニン」と呼ばれるものです。
甘柿、渋柿ともに幼果期には渋みがありますが、甘柿は果実が成熟する過程でタンニンの性質が水溶性から不溶性に変わります。
人間の舌は、だ液に溶けた物質の味を感じるしくみになっていて、水溶性のタンニンはだ液に溶けるため食べたときに渋さを感じます。
しかし、不溶性のタンニンはだ液に溶けないので渋さを感じないのです。つまり、タンニンが水溶性か不溶性かによって渋柿か甘柿かが決まるのです。
甘柿に見られる黒いはん点(ゴマと呼ばれる)は、不溶性に変わったタンニンが酸化したために黒くなったもので、甘柿のしるしといえるのです。
お天気豆知識(2024年10月23日(水))


渋柿はそのままだと渋くてとても食べることはできませんが、干柿にすることでおいしく食べることができます。では、どのようにして渋柿がおいしい干柿に変わっていくのでしょうか。
干柿を作るには、まず、渋柿の皮をむき軒下などにぶらさげます。果物は表皮を通して外呼吸、その内部で内呼吸をしていますが、皮をむいて干すことによって表面が乾燥して固くなり、外呼吸ができなくなります。
すると、内呼吸が活発となった渋柿は、内部で化学反応を起こし、微量のアセトアルデヒドを発生させます。
このアセトアルデヒドの作用で、渋みのもとであるタンニンは水溶性から不溶性に変化し、結果、渋みがとれるのです。また、渋柿の水分がなくなり乾燥することで、柿の中の糖分が凝縮されて甘みも濃くなります。
つまり、干柿は水溶性のタンニンが不溶性になることで渋みが無くなり、さらに糖分が凝縮されることによって甘い食べ物となるのです。