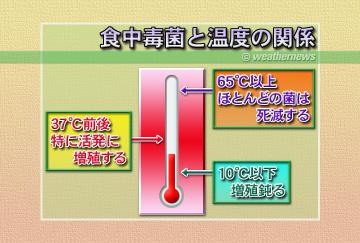スーパーや八百屋でよく目にする果物、バナナ。バナナの高さは1.5から10メートルにも達しますが、実は木ではなく、巨大な草なのです。バナナの栽培は紀元前5000年から1万年ごろに始まったとされ、人間が最初に栽培した果物ともいわれています。
バナナがよく生育するのは、赤道をはさんで南北30度以内の熱帯・亜熱帯地域で、年間降水量2500ミリ、平均気温27度の高温多湿な気候の「バナナベルト地帯」とよばれるところで主に栽培されています。
私たちが口にするバナナのほとんどはフィリピンやエクアドル、台湾などの輸入品です。日本に輸入されるバナナは青いうちに収穫されますが、その理由は黄色くなるまで待つと甘みや香りが失われ、すぐに傷んでしまうからです。
もう一つの理由として、熟したバナナには日本に生息していない害虫が寄生する恐れがあるため、植物防疫吠しょくぶつぼうえきほう)で黄色いバナナの輸入が禁止されているのです。
ちなみに、買ったばかりのバナナは黄色ですが、熟すにつれ黒い班点が皮に現れます。これは「シュガースポット」とよばれ、甘みが増している証拠で、食べごろを教えてくれるサインなのです。
身近なのに意外と知らないバナナの魅力を改めて見直してみませんか。
お天気豆知識(2025年04月27日(日))


一本600円。何の値段だかわかりますか。これは1950年代のバナナ一本の値段を現在の物価に置き換えたものです。1903年の4月に商業用輸入が始まってから約50年後の1950年代でもバナナは高級な果物とされていました。
その理由はバナナが非常に傷みやすい果物で、当時は輸送が困難だったためです。今では輸送技術が発達したため、身近な果物になりました。
では、デリケートなバナナがどのように私たちの手元に届くのでしょうか。青くてかたいうちに収穫されたバナナは13度から14度に保冷され、船で青い状態のまま運ばれます。
そして陸揚げされた青いバナナは、黄色くなるまで「室(むろ)」と呼ばれる倉庫に置かれます。ここでは植物ホルモンであるエチレンガスを入れ、温度や湿度を調節しながら追熟(ついじゅく)を行います。このようにして甘みが増して黄色くなったバナナはようやく店頭に並び、私たちの手に届くのです。
ちなみに買ってきたバナナは15度前後の常温に置き、冷蔵庫には入れないでください。また、バナナを谷型に置くとバナナ自身の重みで下の部分がつぶれて傷みます。負担のかからない山型に置くとよいでしょう。
今は身近な存在となっているバナナですが、上手に保存し、これからも手軽な果物として付き合っていきたいですね。