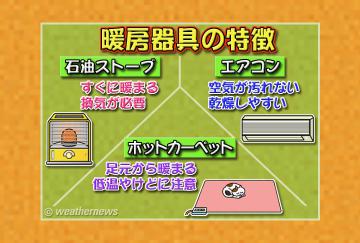長野県の北八ヶ岳に、縞枯山(しまがれやま)という名の山があります。
縞枯山を含む北八ヶ岳連峰の、主に南向きや西向きの斜面では、「縞枯れ(しまがれ)」という現象を見ることができます。
縞枯れとは、針葉樹林帯の一部が横一列の帯状に枯れてしまい、それが山の斜面に何列も並ぶことで、白い縞模様を作り出すものです。
針葉樹が枯れてできた縞模様は、少しずつ山頂部に向かって移動しています。その速さは平均すると、1年で1.7メートルほどで、大変ゆっくりしたものです。
縞枯れ現象は北八ヶ岳だけではなく、関東山地、志賀高原、奥日光、南アルプス、紀伊半島の大峰山(おおみねさん)などでも小規模ながら確認されています。これらの山に登ることがあったら、ぜひその珍しい現象を見つけてみたいものですね。
お天気豆知識(2025年11月13日(木))


山の斜面に現れる不思議な模様、縞枯れは、どのようにして作り出され、なぜ山頂へと移動するのでしょうか。
まず、木を帯状に枯らす原因は数十年に一度という特に風の強い台風などが、樹木を倒すためだと考えられています。斜面の一部の樹木が枯れて葉が無くなると、それまで風や日差しから守られていた土壌が直接強風や強い日射を受けるようになり、特に日当たりの良い南斜面では地面が乾燥していきます。
そして、乾燥した土壌に立つ樹木もやがて枯れてしまいます。このように、樹木が枯れてしまった場所のすぐ後ろでは、日射や風による土壌の乾燥で同じように木が枯れていくのです。
しかし、執と樹木が枯れても山全体が枯れてしまうことはありません。縞枯れの間に生える元気な樹木は背丈を伸ばして防風林の役目を果たします。その後ろに風が弱く日差しも和らげられた、樹木にとって恵まれた環境が作られます。そのため、縞枯れの後ろでは執と幼木が育っていくのです。
樹木が枯れた後に新しい生命が育っていく関係が、移動しているように見える縞枯れを作っているというわけです。