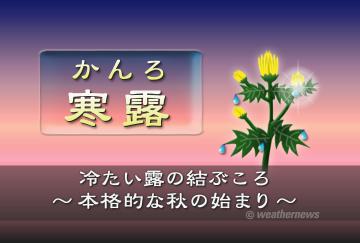季節が秋から冬に変わり始める頃、国境を越えて日本にやってくる鳥たちがいます。
季節によって移動する鳥の中でも、越冬地と繁殖地が異なり、毎年定まった季節に移動を繰り返す鳥を「渡り鳥」と呼んでいます。日本で秋や冬に見られる渡り鳥は、ツルやハクチョウ、ガンといった「冬鳥」と呼ばれる鳥たちです。
日本でのツルの越冬地は、主に鹿児島県の出水市(いずみし)と山口県の周南市(しゅうなんし)です。日本に飛来するツルの第一陣は10月の上旬にやってきます。
この少し前から、シベリア大陸のバイカル湖の南では、冷たい空気を持った高気圧が頻繁に発生します。この高気圧は南東に移動して日本付近に張り出し、北西の冷たい空気を吹き出し季節風となります。ツルはこの季節風に乗って日本へと飛来をするのです。
凍りついた大地となっていたシベリアも、夏になると広大な湿原地帯が広がり、子育てに最適な場所になります。日本で冬を越したツルは、春には再びシベリアへと旅立っていくのです。
お天気豆知識(2025年10月09日(木))


渡り鳥は、なぜ、正確に遠く離れた目的地にたどり着くことができるのでしょうか。
渡り鳥が方向を知るにはいくつかの仕組みがあるようです。その一つに、天体をコンパスとして利用する方法があります。
昼間に渡りをする鳥は、太陽と自分のいる位置とを比較することで、渡りの方向を決めることができるようです。この方法を太陽コンパスといいます。一方、夜間に渡りをする鳥は星を見て方向を決めます。北極星とその周辺にある星座を手がかりにしているのだといわれています。この方法を星コンパスといいます。
ただ、雲が広がっている日のように、天体コンパスがたよりにならない時もあります。そのため、渡り鳥たちはこのほかにも、風や音波、地磁気、地形などあらゆる方法を総動員して、方向を決定しているのです。
しかし、このような「渡りの道しるべ」はあっても、近年ツルたちが地上に降り立つための場所は、減少しています。人間による土地開発のために、湿原や湿地、水田などが少なくなっていることが原因のひとつと考えられています。
世界的にも湿地などは急速に失われつつあり、ツルたちは深刻な事態に直面しているといえるでしょう。