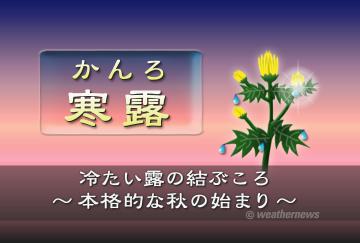秋風にゆらゆら揺れている花といえば、コスモスが思い浮かぶのではないでしょうか。
コスモスは、メキシコ原産のキク科の一年草で、日本には明治時代に伝わったとされています。
日本の花と言えば「桜」が定番ですが、コスモスは花弁が桜に似ていることから、秋桜(あきざくら)という和名も付けられており、今では日本の風景に自然にとけこんで、すっかり秋の代表的な花となっています。
もともとの「コスモス」の名前は、ギリシャ語のコスモス(kosmos)から来ています。ギリシャ語のコスモスには「整頓、装飾、秩序」という意味があり、また、英語(cosmos)には「宇宙」の意味も含まれています。
星がきれいにそろう宇宙と花びらが整然と並ぶコスモスの姿に、共通するイメージがあるのかもしれません。
お天気豆知識(2025年10月06日(月))


コスモスの花をよく観察してみましょう。
コスモスには8枚の花びらがありますが、これは舌状花(ぜつじょうか)と呼ばれる花の一つです。この部分は種を結ぶことはありません。
そして、舌状花の内側には黄色のまるい部分があります。
これは筒状花(とうじょうか)と呼ばれる小さな黄色い花が密集しており、これが種をつくる部分です。つまり、コスモスの花は小さな花がたくさん集まって一つの花を形成しているのです。
星がたくさん集まってできる宇宙と同じように、小さな花が集まっているコスモスは一つの小さな宇宙とも言えるでしょう。