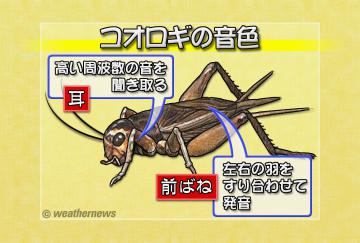この時期になると話題にのぼるのが秋の味覚の王様、まつたけです。
北は北海道から南は九州までと日本全国に生えており、生産量が多いのは長野県や岩手県などです。まつたけはふつうアカマツの林に生えますが、寒い地方ではツガの天然林、エゾマツやトドマツの林にも発生し、ときにはクロマツの林でも見られます。
まつたけは味の良さだけでなく、「香りまつたけ、味しめじ」というように香りの良さも特長です。そのまつたけの味わいは、成長の度合いによって変化します。
土から顔を出したばかりのまつたけは、かさと軸の境がはっきりとしません。その後しばらく経つと、まつたけのかさがはっきりと確認できるようになり、このときがまつたけの最も味の良いときと言われています。
また、さらに成長がすすんでかさがだんだんと開いていき、それが8割ほどに達したときのまつたけは、最も香り高いものになります。
つまり、まつたけの味が好みの方は、かさが開きはじめる直前のものを、香りが好みの方は、かさが少し広がったものを選ぶとよいでしょう。
お天気豆知識(2025年09月26日(金))


まつたけも、旬の時期にとれたものが一番美味しく感じられます。では、まつたけの旬とはいつなのでしょうか。
まつたけの成長は地中の温度が19度まで下がったときに始まり、15度に達したときにその成長が止まるといわれています。そのため、まつたけの旬と言えば地中の温度が15度に達したときといえそうです。
また、地中の温度が19度から15度まで下がるまでの期間、とりわけ、温度が初めて19度まで下がった日から数えて、4日後からの20日間に雨が多く降ると、まつたけの生産量も多くなる研究結果があります。
実際に、この期間中の降水量が多い年は生産量が多くなり、降水量が少ない年は生産量も少なくなるという関係が出ています。ただし、降水量も一概に多ければいいというものではなく、まとまった雨が数日おきに降って、土の中の水分が保たれている環境が、まつたけの生育には適しているのです。
このように秋の長雨は、味覚の秋の王様、まつたけを満喫する上で欠かせないものだったのです。