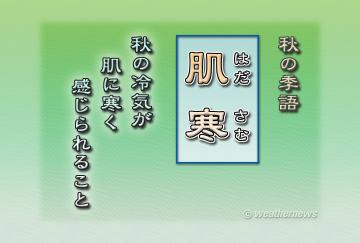9月23日は二十四節気の一つ秋分です。この日は「秋分の日」として祝日にもなっているので、二十四節気の中でもなじみ深いものです。
秋分は、9月20日の彼岸の入りと26日の彼岸の明けの中間に位置することから、「彼岸の中日(なかび・ちゅうにち)」と言われています。この日は祖先を敬い、亡くなった人をしのぶ日とされてきました。
そもそも彼岸とは仏教の言葉であり、仏教においてはご先祖様のいるあの世は太陽の沈む西の方角にあると信じられてきました。このため、太陽が真西に沈む彼岸の中日は、極楽浄土に想いをはせながらご先祖様の供養をし、自らを反省するのにふさわしい日とされてきたのです。
また、秋分は昼と夜の長さがほぼ同じになるころでもあります。秋の彼岸を過ぎると「短夜(みじかよ)」から「夜長(よなが)」へと移ります。
暑さ寒さも彼岸までというように、過ごしやすく物事に集中しやすい季節になります。読書や芸術など、思い思いの秋の夜長を楽しんでみるのもいいかもしれませんね。
お天気豆知識(2025年09月22日(月))
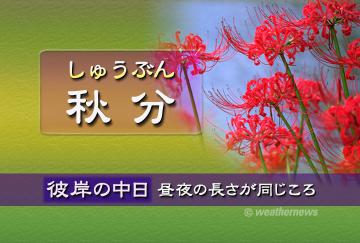

秋が旬の魚と言えば、秋刀魚(さんま)が挙げられますが、一年中、出回っているサバやカツオも、秋にとれるものは美味とされていて、特に秋鯖(あきさば)や秋鰹(あきがつお)などという言い方をします。
サバは、日本の近海の海流を回遊するマサバと、南方の暖かい海を回遊するゴマサバが一般的です。特に秋に漁獲されたマサバは、脂質が20パーセント前後と高く、コレステロールや中性脂肪を低下させるIPAや、脳の老化防止に効果があるDHAを豊富に含みます。また、皮にビタミンB2を多く含んでいるので、皮ごと食べるのが良いでしょう。
次に、カツオは旬が初夏ですが、実は秋の「戻りガツオ」も人気があります。カツオは、例年4月頃、黒潮にのって九州や四国沖を北上し、5月頃、関東に近づいたものを「初ガツオ」と呼びます。エサになるイワシなどを追って、さらに北上したカツオは、9月から10月頃に三陸沖を南下します。この頃の「戻りガツオ」は身が引き締まり、たっぷりと脂がのりきった濃厚な味わいで、「初ガツオ」の比ではないとまで言われるくらいです。たんぱく質が豊富であるのと同時に鉄分が多く、貧血予防によく効くとされています。
そして、「秋」の魚の主役で「刀」の形をした文字通りの秋刀魚(さんま)は、秋が最もおいしく、そのうま味は脂質の多さに左右されます。脂質の量が少ない8月から9月のものは刺身やすしだね向きに食され、10月になると脂質が20パーセント以上になるため、焼き魚にすると香ばしい匂いを漂わせます。サンマもIPAやDHAを多く含むため、コレステロールの増加抑制や発ガン予防、老化防止などの効果が期待できるとされています。
食欲の秋、このような身体にも良いおいしい秋の魚を、それぞれ食べ比べてみてはいかがでしょうか。