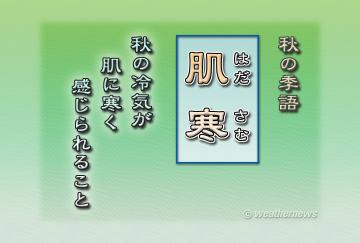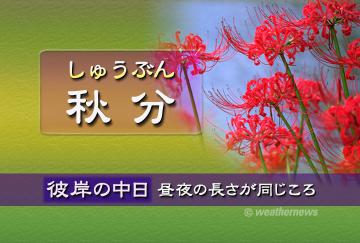10月6日は旧暦8月15日で十五夜にあたります。この日の夜に月を観賞する習慣は、中国の「中秋節」に由来しているとされています。
旧暦では7月を初秋、8月が中秋、9月を晩秋といい、十五夜の月を中秋の名月ともいいます。今のような正確なカレンダーのなかった時代は、満月が折り目の日とされており、特にこの中秋の名月が見られる日は初穂(はつほ)を祝う行事などが行われる、農耕行事と深く結びついたものでした。
ところで、皆さんは月に模様があることはご存じでしょうか。月は私達が唯一肉眼でその表面の模様を見ることのできる天体です。
月の表面の暗く見えるところは平地になっていて「海」と呼ばれます。一方、白っぽく見える部分はクレーターや山、谷、溝などの凹凸のある地形になっています。
このような凹凸は、月表面の光の当たっている部分と当たらない部分との境界付近で見やすくなります。これは、地球において夕暮れ時に影が長くなるのと同じように、月にあるクレーターや山などの影が長く目立つようになって、明暗がくっきりとするためです。
口径の大きな双眼鏡や望遠鏡などを使えば、月の地形まではっきりと見ることができますので、秋の夜長は十五夜に限らず月を眺めてみるのもいいかもしれません。
お天気豆知識(2025年09月21日(日))


月の表面にはクレーターや山脈などがあり、凸凹の地形をしています。その地形の影響で、月の表面には模様が浮かんで見えています。
日本では昔から、それをおもちをつくウサギに見立てて、月にはウサギがいると伝えられてきました。
インドから中国を経て渡ってきた仏教の話によると、その昔、ウサギとサルとキツネの住む山に神様が訪れました。サルとキツネはすばやくごちそうを探して神様にささげましたが、ウサギは神様にささげる食べ物を探すことができませんでした。何も持たずに帰ってきたウサギは、自らをささげようと火をおこしてその中に飛び込み、黒こげに焼け死んでしまいました。そのため、この事を哀れんだ神様がウサギを月に連れ帰ったと言い伝えられています。
細かいところは違っても、日本のあちこちに似たような話があって、この話によって月にはウサギが住んでいる、といわれるようになったのです。
日本では、月の模様といえばおもちをつくウサギが一般的ですが、外国ではカニや女性の横顔、木をかつぐ人というように様々なものに例えられています。月の暗い部分のかたちを見立てたものが多い中、女性の横顔は月の白っぽい部分が肌に、暗い部分が髪に対応しているので、見つけるのは少々難しいかもしれません。
秋の夜長、じっくりと月を観察していろいろ想像してみてください。