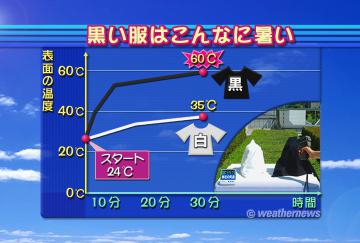天体望遠鏡には、「屈折式」や「反射式」などの種類がありますが、初めて購入する場合は、屈折式望遠鏡がお勧めです。これは、望遠鏡の両端に1枚ずつレンズが付いている最も一般的な天体望遠鏡で、手入れも比較的簡単なので初心者向きといえます。
この望遠鏡でのぞき込む側にあるレンズは「接眼レンズ」その反対側に付いているレンズは「対物レンズ」といいます。どちらのレンズも対象が大きく見えるようにするための働きをし、特に屈折型望遠鏡の倍率は接眼レンズを交換することで変えることができます。
また、対物レンズは光を集めるためのレンズでもあり、これが大きいと光をたくさん集めることができるので、星が明るく見えます。
天体望遠鏡を購入するときは、倍率が大きい物ほどいい気がしますが、いくら倍率を高くしても、対物レンズが持っている性能以上に暗い星を見たり星の表面を細かく観察することはできません。つまり、望遠鏡の性能は対物レンズの大きさが決めているといえます。
もちろん対物レンズが大きくなれば、それだけ望遠鏡は高価になりますが、直径が6センチ程度の望遠鏡でも、肉眼の70倍以上もの光を集めることができるのです。
また、望遠鏡を選ぶ際は三脚(架台)にも気を配りましょう。貧弱な三脚(架台)だと、わずかな揺れでも視界が大きく揺らいでしまい、観測に影響することがあるので、しっかりした三脚(架台)が良いでしょう。
ぜひ、天体望遠鏡を使って、本格的に星空を眺めてみてはいかかでしょうか。
お天気豆知識(2025年08月26日(火))


夏は他の季節に比べて夜になっても気温が高いため、夜空に広がる星々を見るのに適した季節といえます。肉眼で天の川や流れ星を眺めるのもいいですが、天体望遠鏡を使うと、また違った星々の姿を知ることができます。
対物レンズの直径が6センチ程度の望遠鏡は、月や惑星観測などに向いていて、初心者でも気軽に購入できるのでお勧めです。
最もはっきりと見える天体はやはり地球に一番近い「月」で、クレーターなどの細かいところも手に取るように分かります。クレーターの観測には、満月よりも半月や三日月など月が欠けているほうが適しています。これは月に太陽の光が斜めから当たるため、クレーターや山々に影ができて立体的に見ることができるからです。
太陽に近い時には見えませんが、日の出前に東の空に輝いたり、日没後に西の空で輝く金星を望遠鏡で見ると月のように満ち欠けすることがはっきりとわかります。
また、時期を選べば木星の特徴的なしま模様を確認することもできます。「ガリレオ衛星」とよばれる4つの明るい衛星(イオ、エウロパ、ガニメデ、カリスト)を見ることもでき、これらの衛星は木星の周りを回っているため、日ごとに位置が変わるので、続けて観察してみると面白いでしょう。
寝苦しい夏の夜には、天体望遠鏡を使って星々の新しい魅力を見つけてみてはいかがでしょうか。