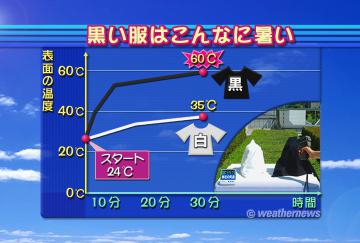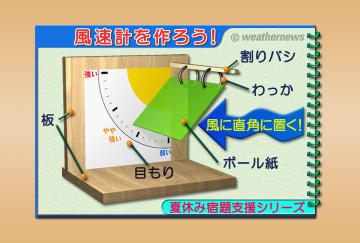これから秋にかけて、赤トンボをよく見かけるようになります。世界には5000種以上のトンボがいて、そのうち日本には200種以上がいると言われています。
たくさんの種類が存在するトンボは、からだの特徴から「均し亜目(きんしあもく)」、「不均し亜目(ふきんしあもく)」の2種類に大きく分類することができます。
「し」とは羽や翼という意味があり、均し亜目は前後の羽の形が似ていて体が小さく細いのが特徴です。イトトンボなどがこのタイプになります。
また、不均し亜目は前と後ろの羽の形が異なり、体は大きく太くがっしりしています。オニヤンマなどはこれにあたります。
「ムカシトンボ」は前後の羽の形は同じで、胴体の太い両方の特徴を持っています。恐竜のいたジュラ紀の化石のトンボと同じ特徴だったため、「生きた化石」と呼ばれ「ムカシトンボ亜目」とされてきましたが、最近のDNAを基にした研究によって、「不均し亜目」ではないかという考え方が多くなっています。
不均し亜目の多くのトンボは、チョウのようにヒラヒラと飛ぶのではなく、一直線に早く飛ぶことができます。これは前後の羽を交互に振り下ろして飛ぶためです。
一方、均し亜目の多くや不均し亜目でもチョウトンボなどの種類は、前後の羽を同じように動かすため、チョウのように飛ぶのが特徴です。
お天気豆知識(2025年08月25日(月))


トンボは別名で「秋津(あきず・あきつ)」とも呼ばれます。そのため、その昔、日本列島はトンボの多い島という意味である「秋津洲(あきずしま)」と呼ばれていました。
日本列島では古くから稲作を行ってきましたが、この水田耕作が、ある種のトンボの生活スタイルにマッチして、トンボの数が増えていったと考えられています。そして日本のトンボの中でも特によく見かける赤トンボも、田んぼと関係の深いトンボの一つです。
赤トンボと呼ばれるトンボは数種類ありますが、一般的にはアキアカネを指します。春になるとアキアカネの卵はいっせいにふ化し、梅雨が明ける頃には羽化をして大空に飛び立ちます。夏から秋にかけて水田で農作業が盛んに行われる頃は、涼しい高原で過ごします。秋になって稲刈りが終わり平野が涼しくなると、アキアカネは一斉に高原から下りてきて、秋雨で湿った田んぼに産卵をします。
アキアカネが成虫になってからの寿命は5ヶ月前後で、秋も終わりの11月頃まで姿を見ることができます。水田が乾いてしまう冬は、田んぼに産みつけられた卵は土の中で越冬し、春になり田んぼに水が張られるのを待ちます。
このように、アキアカネの一生には、田んぼが重要な役割を果たしていたのです。