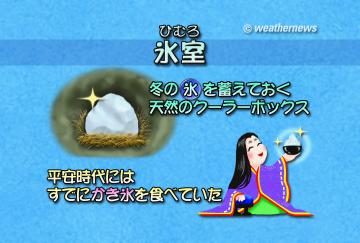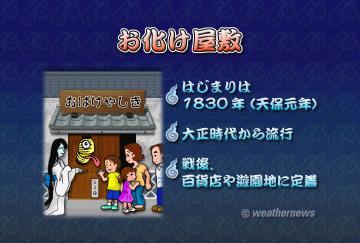ヒマワリは北アメリカ原産の花で、ヨーロッパへ渡った後、ロシアなどへ広まり、17世紀中ごろになって日本へ渡りました。
ヒマワリという名は、読んで字のごとく太陽に向かって回る花という意味です。英語では「sunflower(サンフラワー)」とよび、ずばり太陽の花という意味です。しかし「太陽の方を向いて従う」という意味のsun-followから来ているという別の説もあるようです。
スペイン語では「girasol(ヒラソル)」とよばれ、「girar(ヒラール)」は回る、「sol(ソル)」は太陽を表しているので、太陽について回る花、という意味になります。
ドイツ語では「sonnenblume(ゾンネンブルーメ)」といい、「sonne(ゾンネ)」は太陽、「blume(ブルーメ)」は花ですから、やはり太陽の花という意味になります。
このように、ヒマワリの咲いた花のかたちが太陽に似ているということと、太陽を追うようにして回る性質をもつということから、世界のいたるところで太陽と結びつけられているのです。
お天気豆知識(2025年08月16日(土))


お日さまがカンカンに照りつける夏の代表的な花と言えば、やはり太陽のように咲くヒマワリでしょう。
ヒマワリという名前は「太陽に向かって回る花」という意味に由来しています。しかし実際のところ、花が太陽を追うように回るものは、ヒマワリの中でも限られた種類で、多くは花を咲かせる前に茎の先やつぼみが回転するだけです。
ヒマワリはキク科の一年草で、大輪を咲かせることで知られていますが、大きな花はそれ自体が1つの花ではなく、管状花(かんじょうか)または筒状花(とうじょうか)とよばれる小さな花が1000個以上も集まってできていたものなのです。外側の黄色の花びらは虫を引きつける飾りの役目をし、内側にある小さな花は外側から中心に向かって順番に咲いていき、最後に種をつけます。
また、ヒマワリの高さは平均で2メートルから3メートルと背の高いものですが、背丈は2階建ての家よりも高く、花はマンホールのふたほどの大きさにまで成長したものもあります。