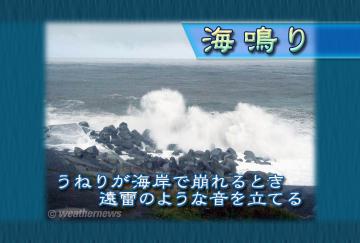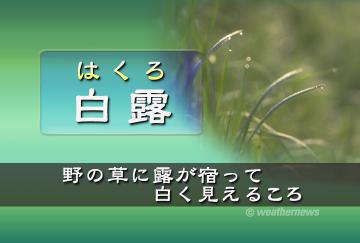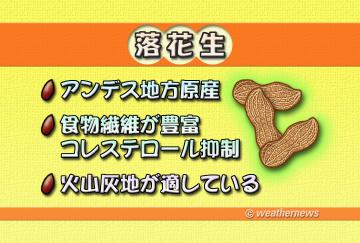7月7日は「七夕」の日です。
七夕は天の川をへだてた恋人同士の織姫(おりひめ)と彦星(ひこぼし)が、年に一度だけ会うことのできる日です。
七夕というと、短冊(たんざく)に願い事を書いて笹竹(ささだけ)に飾る習慣がありますが、実はこの風習は中国から伝わってきたものです。昔の中国では7月7日に「乞巧奠(きこうでん)」と呼ばれる星祭りが行われていました。このお祭りは、女性の願いであった裁縫の上達を祈ることを目的とした行事です。
中国において織姫(おりひめ)は針や糸の仕事をつかさどる星として信仰されていました。そしてこの星祭りは、7月7日に彼女の願いがかなうという伝説にあやかることから生まれたものなのです。
このお祭りでは、針に通した5色の糸が供えられていましたが、日本に伝わってから今の「五色(ごしき)の短冊」が生まれたようです。そして短冊に歌や文字を書き、習字が上手になることを願うようになりました。
今では習字や裁縫の上達だけでなく、短冊に好きな願い事を書くことができるのですから、とても得をしている気がしますね。
お天気豆知識(2025年07月07日(月))


七夕に願い事を書く短冊には、もともとは5つの色が使われていました。
この5つの色とは、青、赤、黄、白、黒のことで、中国の陰陽五行説(いんようごぎょうせつ)という考え方に由来しています。陰陽五行説とは、自然界のすべてのものを木、火、土、金、水の5つにあてはめて説明することができるという考え方です。そして陰陽五行説によればこの5つの色にも意味があり、青は木、赤は火、黄は土、白は金、黒は水を表しているといいます。
しかし、現代の日本では短冊に願いを込めることは変わってはいませんが、短冊の色はあまり意識されなくなりました。逆に、笹竹に飾る短冊や飾り物は次第に派手さを競うようになり、仙台や平塚の七夕などでは大きな吹流しや紙細工の飾り物を付けるなど、けんらん豪華なお祭りとなっています。
7月7日の七夕の時期は、ほとんどの所で梅雨の時期に重なってしまいますが、家族で五色の短冊や飾りを笹につけて梅雨時の楽しみにしてみてはいかがでしょうか。