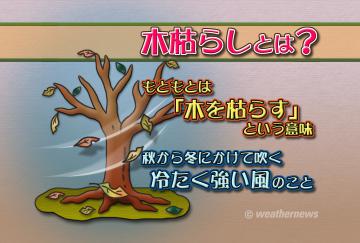6月10日は「時の記念日」です。この記念日は西暦671年6月10日に天智(てんじ)天皇が、水時計を使って初めて時を刻んだことにちなんで1920年に制定されました。
時間の表現には「秒」や「分」、「日」などがありますが、1時間は60分、1日は24時間、といったように決まった数字です。
ただ、1年は365日または366日と、うるう年になると1日多くなります。4年に1回、うるう年があるのは地球が太陽のまわりを一周する時間がぴったり365日ではないからです。地球が太陽の周りを一周する公転周期は365.2422なので、365日に約4分の1日追加することで暦のずれを調整しているのです。
ちなみに、うるう年は4年に1回という法則はよく知られていますが、さらに条件があることをご存知ですか。原則として4で割り切れる年がうるう年になりますが、それには例外があります。100で割り切れる年のうち、400でも割り切れる年はうるう年になりますが、それ以外はうるう年になりません。例えば2000年はうるう年ですが、2100年はうるう年にはならないのです。
普段の生活において、私たちは漠然と時の流れを感じていますが、年に1回の「時の記念日」に時間の大切さを改めて感じてみるのもいいですね。
お天気豆知識(2025年06月09日(月))

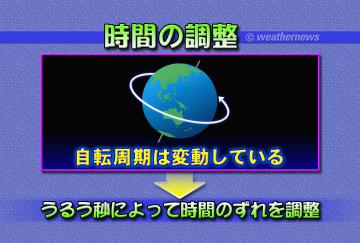
一年が366日になる「うるう年」は耳なじみの言葉ですが、実は「うるう秒」もあることはご存知でしたか。
時間には二つの種類があります。一つはセシウム原子の30万年に一秒しか誤差が生まれないという、きわめて正確な時計です。もう一つは地球の自転に基づく「世界時計」です。地球の自転周期はごくわずかですが変動しているため、原子時計と世界時計の差が一定範囲内におさまるように、うるう秒を設けて時間を調整しているのです。
うるう秒によって調整された時間は「協定世界時(UTC)」とよばれ、多くの国で日常的な時間の基準として使われています。日本の基準時は、この協定世界時に9時間足した時刻となります。
ちなみに、うるう秒の調整は1月1日または7月1日、さらに必要なら4月1日と9月1日の0時前に行います。2017年1月1日にうるう秒の調整が実施されました。たった1秒の調整ですが、うるう秒は時間を正確に刻むためになくてはならないことなのです。
うるう秒をめぐる議論一方で、うるう秒の追加によって、コンピューターシステムに障害が発生する問題が指摘されています。そのため、今後は1秒単位でのうるう秒の調整を実施せずに、原則2035年までに、うるう秒に変わるものを考える議論が進んでいます。(参考:国立天文台ホームページ)