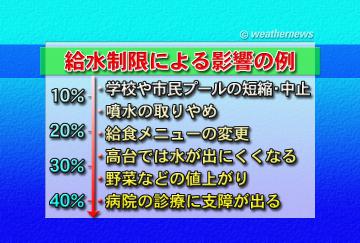43人が犠牲になった長崎県の雲仙岳の大火砕流から3日で32年になります。
1990年11月に始まった雲仙岳の噴火活動は1995年に終息しましたが、この間、頻繁に火砕流を発生させ、大きな被害を出しました。「火砕流」という火山用語を雲仙岳の噴火で初めて知った人も多いのではないでしょうか。
火砕流とは、火山の噴火に伴い、高温の火山灰やガス、岩石などが一団となって高速で斜面を流れる現象です。その様子が雲のようにも見えるため、別名「熱雲(ねつうん)」とも呼ばれ、温度はセ氏数百度から1000度、流れ下る速度は時速100キロ以上にも達します。
火砕流は高温高速であるため破壊力が極めて大きく、通過した地域のほとんどすべてを焼き尽くし破壊します。そのうえ発生してから逃げるのはたいへん困難なため、火砕流は火山現象の中では最も危険なもののひとつとされています。雲仙岳で起きた火砕流は、火砕流の規模そのもので見ると小規模な部類に入り、数万年に一度という頻度で発生するような、極めて大規模な火砕流になると、その到達距離は、火口から100キロ以上に及ぶことがあります。
1902年、カリブ海に浮かぶ西インド諸島マルチニーク島のモンプレー火山で起きた噴火では、火口から8キロ離れた都市が火砕流に襲われ、逃げる間もなく住民2万8000人が全滅したという記録も残っています。
火砕流は発生後の避難が困難なことに加え、発生の予測も難しいため、普段から個々の火山の特性をよく知り、噴火したときに最善の対処ができるよう備えておく必要があります。
お天気豆知識(2025年06月01日(日))


火山が噴火すると、それに伴っていくつもの危険な現象が起こることがあります。
例えば、よく知られているものに溶岩の流出があります。地表を流れ下る溶岩は「溶岩流(ようがんりゅう)」といい、溶岩流が通るとその高い温度によって建物や道路、田畑は全て焼失してしまいます。
また、噴石は、噴火によって火口からふき飛ばされた岩石などの噴出物のことで、火口から数キロメートル離れた場所まで飛ぶこともあります。
火砕流は、高温の火山灰や岩石、火山ガス、空気、水蒸気が一体となって山を流れ下りるもので、最も危険な現象のひとつです。その速さは時速数十キロメートルから数百キロメートルで、その流れの先にいた場合、避けることは不可能だといわれています。
さらに、火山活動が衰えてきてもなお注意しなければいけないものに土石流があります。土石流は岩石や土砂、倒された樹木、火山灰などが水と一緒になって流れ下りるもので、たいてい時速数十キロメートルの速さで進み、かなり離れたところまで流れていくため危険です。雨や雪解け水などによって誘発されることも多いため、大雨の際は発生の可能性が高くなります。そのため火山が噴火した時は、火山活動はもちろんのこと、そのごの天気も把握する必要があるのです。