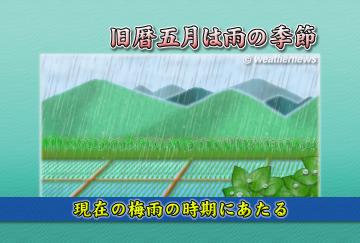5月は別名、早苗月(さなえづき)や田草月(たぐさづき)とも言われており、ちょうど田植えの時期にあたるためについた名前です。
昔は陰暦を使用していたため実際には6月頃を指しており、田植えもその頃でした。しかし、現在はコシヒカリなど早く田植えをする品種が人気であることや、機械で田植えをするために、手で植えていた頃よりも苗が小さい状態で田植えをするようになっています。そのため、地域差はあるものの、大型連休のちょうど今あたりが田植えのピークになっている所が多いようです。
田植えはもともと村の共同作業であり、同時に神事でもありました。今でも全国の多くの神社には、御田植祭(おたうえまつり)、または御田植神事(おたうえしんじ)などと呼ばれる伝統行事が残っています。
この行事は田の神様をよろこばせて秋の豊作を祈る大切なもので、無形民俗文化財に指定されているものも多くあります。
毎年6月14日に行われる大阪住吉大社の御田植神事や千葉県香取神宮、三重県伊勢神宮、熊本県の阿蘇神社などで行われるものが代表的な田植えの祭りとして挙げられます。
お天気豆知識(2025年05月03日(土))


御田植祭は地域や神社により多少の違いはありますが、実際に田植えを行うものと、田植えのまねをするものがあり皆、古風な装束を身にまとい行列に参加します。
笠をかぶって、赤いたすきをかけた女性は「早乙女(さおとめ)」と呼ばれ、田植え歌を歌いながら田植えをします。
腕には手甲(てっこう)と呼ばれる布や皮でつくられた覆いをして、足下は脚絆(きゃはん)をつけて歩きやすくします。
真新しい手ぬぐいに赤いたすきをかけた姿は美しく、凛々しささえ感じます。
今では機械化がすすみ、日常で早乙女の姿を見ることはなくなってしまいましたが、御田植祭に登場する早乙女の姿は風物詩として大切にしたいものです。