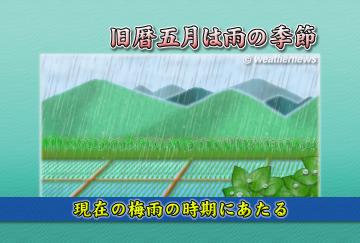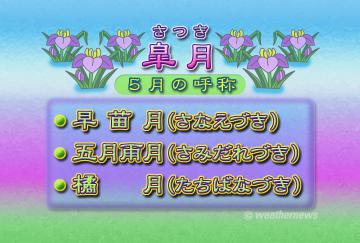5月2日はエンピツの日です。鉛筆の後ろには、2Hや2Bなどの数字とアルファベットの組み合わせが書かれているのを目にするでしょう。これらは鉛筆の濃さを表していますが、大変多くの種類があるのです。
まず、アルファベットにはHとFとBがあり、Hは英語の「硬い」を意味するHARDの頭文字からとられ、Fは英語の「しっかりした」を意味するFIRMの頭文字から、Bは英語の「黒い」を意味するBLACKの頭文字からとられています。
鉛筆はH、F、Bの順番でより濃くなっていきますが、濃さの段階はこれと数字との組み合わせによってさらに細かく分けられ、全部で17種類にのぼります。
JISの定義では、Hは9Hまであって、数字が大きくなるほど薄くなり、Bは6Bまでで、数字が大きいほど濃くなり、これらの間にFとHBをはさみます。また、さらに硬い10Hと、より黒い10Bまでの22種類を販売しているメーカーもあります。
このように鉛筆は細かく濃さの段階が分けられ、用途に応じて使い分けができる工夫がされているのです。
お天気豆知識(2025年05月01日(木))


鉛筆の形には、六角形や丸形のものがあり、それぞれ用途の違いがあります。
鉛筆は、親指、人差し指、中指の3つの指で持つため、3の倍数である六角形は持ちやすく、文字が書きやすいのです。そのため六角形のものは筆記用に多くなっています。
一方、丸形のものは指あたりがよく、持ち替えやすいのです。くるくると回しながら使え、塗りつぶしやすくなっています。そのため色鉛筆に多いのです。
また、色鉛筆の芯は軟らかいため、丸形の方が木軸が一定の厚さなのでどんな方向からの力に対しても丈夫であり、軟らかい芯を支えるのに適しているのです。
このように鉛筆は目的に応じて使いやすいように工夫がされています。最近では、鉛筆を使うことが減っている方も多いかもしれません。たまには鉛筆を利用して優しい書き心地を実感し、その良さを見直してみませんか。