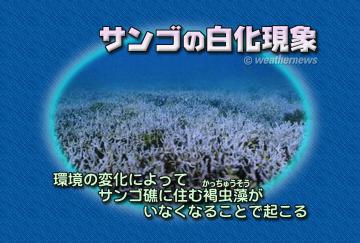暖かな陽射しに誘われて、外にでてみると、あちらこちらに春の訪れを感じることができます。たとえば、空き地や道ばたなどに咲くタンポポです。
日本には20種類以上のタンポポがあり、大きく在来種のニホンタンポポ、外来種のセイヨウタンポポに分けられます。
ニホンタンポポはエゾタンポポや中部地方以北に生息するシナノタンポポ、関東地方で見られるカントウタンポポ、東海地方のトウカイタンポポ、関西以西に生息するカンサイタンポポなどといった種類があり、地域の名前がつけられています。
また、四国や九州では、黄色の花をつけるものよりも、シロバナタンポポと呼ばれる白い花のタンポポが多く分布しています。
一方のセイヨウタンポポは、その名の通り明治時代にヨーロッパから野菜として入ってきたものです。こちらは、日本中に生息しており、いまやニホンタンポポをしのぐほどたくさん見ることができるようになりました。
お天気豆知識(2025年03月10日(月))


タンポポは、平地から山の上まで、またコンクリートに覆われた都市でも生息できるので見つけるのは簡単です。見つけたタンポポがセイヨウタンポポかニホンタンポポか見分けてみましょう。
花を横から見てみると、総苞片(そうほうへん)と呼ばれる花の首の部分が下向きに反り返っているものが外来種であるセイヨウタンポポです。
在来種は、白い花をつけるシロバナタンポポがわずかに反り返っているだけで、他のものは反り返ることはないのです。探してみると、セイヨウタンポポの方が多く発見できるはずです。
セイヨウタンポポがこれほどまで広まった理由は、乾燥に強く、またコンクリートなどによってアルカリ性になった土壌でも十分育つ性質をもっているため、都市化された現在に適応した品種だからのようです。
また、在来種のニホンタンポポと違って、セイヨウタンポポは交配しなくても種子を作り出すことが出来ることも理由の一つのようです。
繁殖力の強いセイヨウタンポポは、春に限らず花をつけ、暖かい地域では冬でも花を咲かせます。春でもないのにタンポポをみつけたら、おおむねセイヨウタンポポと考えてもいいでしょう。