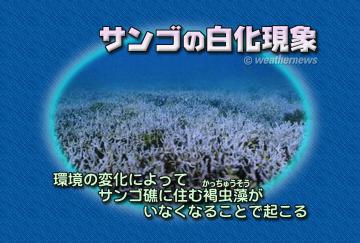3月5日は二十四節気のひとつ、啓蟄(けいちつ)です。「啓」は「ひらく」、「蟄」は冬の間、地中で冬眠している虫をさし、つまり「啓蟄」はこれらの虫たちが冬眠から目覚めて穴からでてくるという意味があります。
アリ、トカゲ、ヘビ、カエルなどの生物を「蟄虫(ちっちゅう)」といい、啓蟄のころに鳴る雷のことを「蟄雷(ちつらい)」といいます。
蟄雷(ちつらい)は、春の雨とともに鳴る雷は冬眠中の虫たちの目を覚ます、と言われていることからきていて、虫だしの雷ともいいます。
啓蟄を迎え、暦の上では虫たちに春が訪れたことになりますが、虫たちが実際に活動を始めるのはもう少し先のようです。
虫が活動を始める目安として、一日の平均気温が10度以上というのがあり、平年値をみてみると、啓蟄のころに10度以上になっているのは沖縄や九州南部など、一部の地域に限られます。
まだ多くの地域では10度以下の気温であり、虫の姿を目にするようになるのはもうしばらく先のことになります。
お天気豆知識(2025年03月04日(火))
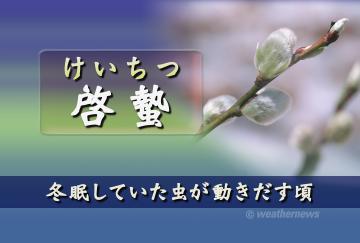

春が一歩ずつ近づき、庭園などでは「こも焼き」が行われる時期となりました。こも焼きは虫がはい出てくるとされる「啓蟄」の前までに行います。
そのこも焼きとはどういうものでしょう。「こも」とは、わらなどをあらく織ったむしろのことで、前年の「立冬」のころに木に巻き付けられます。
公園や街路樹、庭園の松の木などに、冬の間、腹巻きのようなこもが巻かれた姿を見ることができます。一見、寒さ対策なのかとも思いますが、これは害虫駆除の作業なのです。
寒さが厳しくなると、越冬のため枝先から下りて枯れ草などに潜り込む虫の習性を利用したもので、冬の間、樹木の天敵である虫を暖かいこもの中に誘い込みます。そして、暖かい春になって虫が活動を始める前にこもを取り外して虫ごと焼いてしまうのです。
こも焼きの行事で有名な岡山の後楽園では、現在、害虫は薬によって駆除しているので、こもによる害虫駆除の意義は薄れていますが、こもを巻く「こも巻き」は初冬の風物詩、こもを焼く「こも焼き」は春を告げる風物詩として続けられています。
後楽園には昔ながらの季節の行事を見るために、毎年多くの観光客が訪れています。