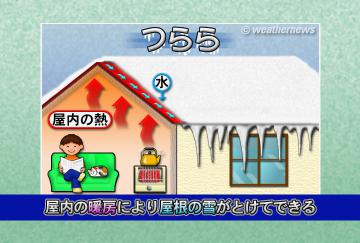5月はひょうの多い季節です。ひょうとは、空から降ってくる氷のうち直径が5ミリ以上のものですが、時にはびっくりするような大きさのひょうが降ってくることもあるのです。
例えば、1917年6月29日、埼玉県において、かぼちゃ大のひょうが降ったことが記録に残っています。また、1933年6月14日には兵庫県播磨地方で疾風をともなって、にわとりの卵くらいの大きさのひょうが降りました。このときは死傷者が174人も出る惨事となりました。
そして、2000年5月24日に茨城県南部と千葉県北西部に、ミカン大のものが降りました。このとき日本列島は西からの高気圧に覆われており、日中は気温がどんどん上がりました。しかし、日本海には上空に寒気を伴う低気圧があったため、上空と地上の気温差が大きくなり雷雲が発達したのです。
このときのひょうの影響で負傷者は100人以上に達し、千葉県では野菜やくだもの、花木などを中心に農作物・農業施設関係に66億円の被害が発生しました。
ひょうは大きさが大きいほど落下速度も速まり、その衝撃も強まります。ひょうの降りやすい地域では、いかにひょうの被害を防ぐかが重要な課題なのです。
お天気豆知識(2025年05月06日(火))


ひょうは、直径が10ミリ程度のものでも時速50キロで落ちてくるため、窓ガラスが割れるなどの被害を受けます。
特に農作物に与える被害は甚大で、大切に育てた作物がひょうに当たるとあっと言う間にダメになってしまうので、農家にとってはいかにひょうを防ぐかが重要になります。
そのため、果樹園などでは防ひょうネットとよばれるものを利用しています。防ひょうネットで農作物を覆うことにより、被害を未然に防ぐことができるのです。
ただ、いつもネットをかけていると農作物に必要な日射しの妨げになるため、ひょうが降りそうな時を見計らってネットをかけなければなりません。
農家の人はいつも空とにらめっこしながら農作物を大切に育てているのです。