これからは寒暖を繰り返しながらも、ますます春らしい日が多くなっていきますが、例年、春には日本各地で強い南西の風が吹き荒れることがあります。
この強風は、「春の大風」といわれ、春に初めて吹けば「春一番」、桜の咲く時期に吹けば「花散らし」ともよばれます。
この風は、漁船を転覆させたり、飛行機を乱気流に巻き込んだりするほか、その暖かさによって雪崩を引き起こすこともあるため、防災上も正確な予報が求められる現象です。
この南西の強風を生み出す主な原因は日本海で発達する低気圧です。日本の南の海上にある高気圧の勢力が強まる春先には、低気圧が日本海を発達しながら北上することが多くなります。
そんなときの天気図は、南に高気圧、北に低気圧という配置になっていて、日本には北の低気圧に向かう南西風が吹きつけるのです。
そのため日本海で低気圧が発達する場合には、この南西の強風が吹きやすいといえるでしょう。
お天気豆知識(2025年02月28日(金))
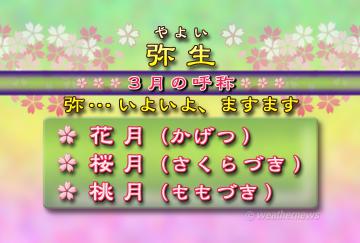

春に吹く南西の強風は、日本海側に発達した低気圧がある場合に現れやすいものです。しかし、その低気圧が発達していない時でも強い南西風が吹くことはあります。
この場合、どのような仕組みで起こるのでしょうか。それは、暖かく軽い空気が上にあり冷たい空気が下にある場合、下の空気が押さえられて通り道が狭くなり、風が地上付近に集中して勢いを増すことにより起こるのです。
一般に大気は上へ昇るほど冷やされるので、地上に近いほど気温は高くなりますが、ときにはその関係が逆転して、下の層よりも暖かい空気が上にくることもあります。
空気が暖かいということは軽いということでもあるため、その場合の下側にある重たい大気にとって上のより暖かい空気は天井のような存在になります。そのため上の軽い空気の層が高くなったり低くなったりして上下に波打っていると、それより下側を吹く風の通り道も広くなったり狭くなったりします。
天井の役目をする軽い空気の層が低く、下を流れる風の通り道が狭くなっている状態は、ちょうど水の流れるホースの先端をつまんだ状態と表現することができます。つまり、水が勢いよくながれるように、下側の空気が強風として吹くのです。
春の南西強風は、低気圧が日本海で発達したときにだけ注意すればよいというものではなく、上空の大気にも目を向けなければ予想できない複雑な現象なのです。



