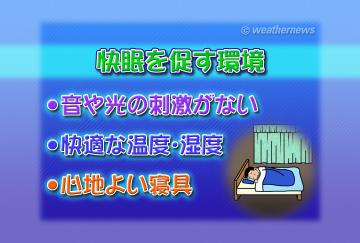晩秋から初冬にかけて一日の内に降ったりやんだりする雨のことを「時雨」といいます。
ちょうど今頃の時期に、日本海側の地域でしぐれることがあり、昔は陰暦10月のことを「時雨月」ともいいました。
11月に入ると西高東低の冬型の気圧配置になる日が多くなり、大陸から日本列島へ向けて冷たい季節風が吹くようになります。冷たい季節風はもともと乾いた大陸から吹く風なので比較的乾燥していますが、日本海の上を渡ってくるときに、湿った風に変わります。
日本海が海面付近の空気に比べて暖かいため、水蒸気がたくさん供給されるからで、そのとき上昇気流も発生します。冬の日本海の上昇気流は、一定の間隔をもって発生するため、この上昇気流によってできる雲も一定の間隔で行列をつくります。
これらの雲が地上を通過するときに雨を降らし、通り過ぎると雨は止み、時には日が差し込むこともあります。雨が降ったり止んだりする時雨のしくみは、日本海の雲の行列のためなのです。
お天気豆知識(2024年11月25日(月))


時雨は日本海側の地域でよく見られる現象で、日本人には昔からなじみ深いものです。
京都では「北山時雨(きたやましぐれ)」といい、詩にもよまれるほど有名で、冬支度の合図とされてきました。
この北山時雨をもたらす雲は、日本海から丹波高地を通り、丹波高地の山あいを抜け、京都盆地の北部まで流れてやってくるのです。
また、しぐれた日にはすてきな「おまけ」がつくことがあります。それは「虹(にじ)」です。時雨が降った後日ざしが出ると、空気中に残った雨粒に太陽光線が当たって、虹ができやすいのです。
哀愁の漂う晩秋から初冬、時雨が降っている間、きれいな虹が見られるのを楽しみにしてはいかがでしょうか。