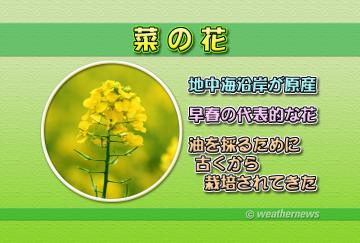夜空の星には、明るくてすぐに見つかる星からやっと見えるくらいの暗い星、そして望遠鏡を使わなければ見えない星、とその明るさは様々です。
星の明るさを表現するのには、「等級」という単位が用いられています。等級の数字が小さいほど明るい星で、1等級の先は0等級、マイナス1等級という具合になります。
また、1等級の明るさを持つ星を1等星とよびます。星座を楽しむときに方位を教えてくれる北極星の明るさは2等級です。
夜空にひときわ明るく輝いているシリウスはマイナス1.5等級、満月は平均でマイナス12.7等級、そして、直視できないほどまぶしい太陽はマイナス26.7等級になります。
星の明るさは、地球との距離にも関係しています。星自体がいくら光を放っていても、地球から離れすぎていてはさほど明るく感じません。
星を仮にある一定の距離に並べたときに見える明るさを絶対等級と呼んでいます。この絶対等級を使うと、明るい太陽でも4.8等級でしかありません。
シリウスは1.4等級ですから太陽よりも明るく、北極星にいたってはマイナス3.6等級となって、大変強い光を放っていることがわかるのです。
お天気豆知識(2024年09月28日(土))


星の明るさの基準である等級は、今から2000年以上前にギリシアの天文学者ヒッパルコスによってつくられたといわれています。
彼は夜空に輝く星を、肉眼で見つけられる限界の明るさを6等級、最も明るいものを1等級、というように明るさによって6つに分類し、それぞれの星に等級を与えました。
そして19世紀になって、ハーシェルという学者が、等級がひとつ減るごとに、明るさがおよそ2.5倍になることを発見し、それを引き継いだポグソンが星の等級を数式で表現することに成功し、それまでの1等級の明るさを持つものの平均を1として、6等級の明るさの100倍に決めたのでした。
つまり、1等星は6等星の100倍の明るさに相当するというわけです。
また、このことによって等級にはマイナスの値も存在するようになるとともに、小数点以下の値も用いて表現されるようになりました。
現代の科学技術の進歩は目覚ましく、国立天文台が運用しているすばる望遠鏡を使えば、肉眼で観察できる限界といわれる6等級の、さらに約6億分の1の明るさである、28等級まで観察することができるほどになっているのです。