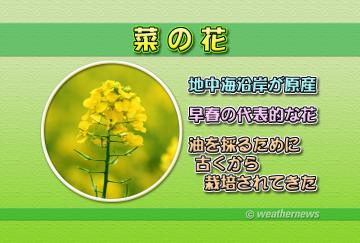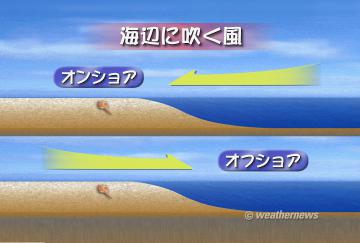今年(2024年)は、9月17日が中秋の名月です。
日本では、1873年(明治6年)に太陽をもとにした暦(グレゴリオ暦)が作られるまで、月をもとにした暦(太陰暦)が使われていました。昔は月の形を見れば、その日が何日ごろか分かるようになっていたのです。
つまり、新月になる日を、その月の朔日(ついたち)と数え、三日月は、その名の通り3日目を意味します。そして、半月(上弦)になるころが7日目。さらに月が丸みを帯びて満月になるころは、新月から数えて15日目なので、十五夜と呼ばれます。
その中でも、旧暦8月15日の月は「中秋の名月」と呼ばれ、昔から月を観賞する風習がありました。月見は平安時代から始まったとされ、旧暦8月15日の月を「名月」と呼ぶようになったのは、室町時代からと言われています。
この日の月が特別な意味を持つようになったのは、旧暦8月15日が初穂祭の日に当たり、農耕行事のひとつとされていたことにもよります。
芋やだんご、ススキの穂などが供えられるのも、同じく農作物の収穫を祝う風習から来ていると考えられています。
お天気豆知識(2024年09月16日(月))


中秋の名月は年によって違いますが、新暦の9月上旬から10月上旬ころになります。
この時期は西日本や東日本では、秋雨のころと重なるため、月が雲に隠されることが多くなるものの、秋の満月は、低い位置を通るという点で月見には適しています。
一方、冬は太平洋側では晴れることが多く空気も澄んでいますが、月の位置がたいへん高いところにあり、家の中からは見づらくなります。
秋の満月と冬の満月の高さを比べると、角度にして30度前後も違うのです。このように秋の月が冬の月より低い所にあるのは、一年を通して、満月の動きと太陽の動きが正反対であることが理由です。
太陽の高さが低い冬は、満月は高い空を通過し、夏はその逆になります。太陽が比較的高いところを通る秋も、月は南の低い位置を通るため、秋の月見は体に無理な姿勢を強いることなく、長時間ゆっくりと眺めることができるのです。
普段何気なく見ている月ですが、一度ゆっくりと月見を楽しんでみてはいかがでしょうか。