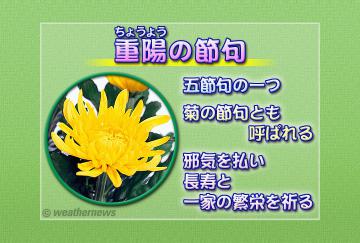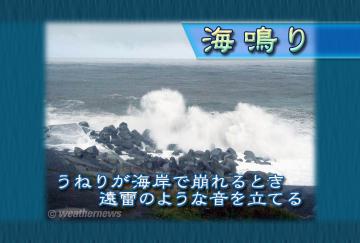9月は大型台風が襲来しやすい時期です。この時期の台風は収穫前の農作物に多大な被害を与えます。
実際に、9月に上陸した台風による耕地の被害面積を見てみると、1954年の洞爺丸(とうやまる)台風と1958年の狩野川(かのがわ)台風、それに1961年に上陸した第2室戸台風の時には8万ヘクタール以上となりました。また、1945年の枕崎(まくらざき)台風は約13万ヘクタールが流失や冠水などの被害にあいました。1959年の伊勢湾台風にいたっては、21万ヘクタール以上と、東京都と同じくらいの面積が被害にあったのです。
このように、9月の大型台風は田畑などに大きな傷跡を残します。「一吹き百万石」という言葉がありますが、これは、台風が一回通り過ぎると百万石(約15万トン)の稲を失ってしまうことを表現したものです。百万石とは、約200万の人々が一年間に食べる米の量に匹敵します。台風が一度やってくるだけで、人々のその後の生活を左右するほど、台風は恐ろしいものだったのです。そのため、収穫前の稲や農作物を台風から守るため、人々は様々な努力をしてきました。
最近では、田植えの時期を早めて収穫時期をずらすことによって、被害を最小限に抑えることに成功しています。また、品種改良や栽培管理などの工夫のほか、より精度の高くなった台風の予報技術を利用することにより、昔ほどの被害がでることは少なくなっています。
お天気豆知識(2025年09月09日(火))


台風がもたらす風や雨により、稲などの農作物は非常に大きなダメージを受けます。
そのひとつが水害です。一日の雨量が100ミリを超えると、冠水する田畑が見られるようになり、200ミリ以上になると、多くの河川が氾らんし、河川沿いの田畑も冠水します。
また、強い風による風害は台風ならではで、強風にあたることで倒れたり落葉したり、茎が折れたりなどの被害が出ます。風速15メートルにもなると、収穫前の稲からはもみがたくさん脱落してしまい、その結果、収量が減ってしまいます。
そして、海岸の近くの田畑で見られる害に、潮風(ちょうふう)害があります。これは台風による強風によって海の塩分が農作物に付着し、塩分が植物の体に浸透して植物の生理機能を低下させ、ひどい場合には枯死する被害です。その被害は海に近い田畑の方が大きくなりますが、海岸から50から100キロ離れた内陸の地域でも発生することがあります。
そのほかにも、台風が日本海にある場合には、南風が山を越えて日本海側に吹き下りる、いわゆるフェーン現象が起きることがあります。ちょうど出穂時期の稲がこの乾燥した高温の風にあたると、穂の先に水分が通らなくなってしまう白穂(しらほ)と呼ばれる状態になりやすくなります。
このように、台風は農作物に恵みの雨をもたらす一方で、様々な形で被害を与えます。台風が接近しているときは、あらかじめ、どのような被害が起こるかを想定して、十分な対策をとることが重要といえるでしょう。