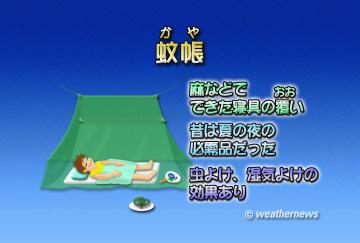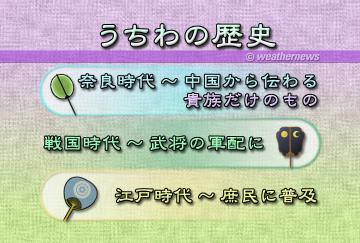夏本番を迎えると太陽の照りつける青い海に出かけたくなりますね。
海の色は、手でその水をすくってみると透明なのにどうして青く見えるのか不思議に思いませんか。この秘密は太陽の光にあります。
地上に降り注ぐ太陽の光は普段は色を感じませんが、実は、赤、橙(だいだい)、黄、緑、青、藍(あい)、紫という様々な色の光が混じり合ってできています。
プリズムに太陽の光を通すと虹のように様々な色が現れることからもそれが分かるでしょう。この太陽の光が海の中に入ると、波長の長い赤や黄色などは海の水に吸収されてしまいます。しかし、波長の短い青い光は吸収されずに残ります。
海が青く見えるのは、太陽の光のうち青の光が残り海の中で散乱するためなのです。
このように海の色の見え方に太陽の光が関係しているとは意外なことですね。
お天気豆知識(2025年07月15日(火))


海の色と言えば、オーシャンブルーという言葉があるように青色を思い浮かべるでしょう。しかし、世界には青以外の色の名前が付いた海があるのです。
例えば、中国大陸の東には黄色の海と書く「黄海(こうかい)」があり、本当に黄色がかった色をしています。これは、主に黄河によって運ばれた黄土によって沿岸部の水が黄色く濁って見えるためで、名前もそれに由来しています。
また、紅(くれない)の海と書く「紅海(こうかい)」は、アフリカ大陸とアラビア半島の間にある細長い形の海です。紅海は、「トリコデスミウム」というプランクトンの増殖によって時々海が赤く見えることから、そう呼ばれるようになったと言われています。
そして、ヨーロッパとアジアの間には黒海(こっかい)があります。黒海の名前の由来には様々な説がありますが、海の色が黒いというわけではなく、晴天が多く温暖な地中海と比較して暗く、荒々しい北の海を表現したものと考えられています。
そのほかにもロシア西部の白海(はっかい)があります。これは10月ごろから結氷し、翌年5、6月まで流氷がただよう海です。その語源には諸説ありますが、一年の半分以上が氷に覆われているためまさにふさわしい名前と言えるでしょう。※実際に水が赤い海も存在します。オーストラリアのタスマニア島のバサースト湾は、湿原の植物由来のタンニンを含んだ川の水が比重の関係で表面を覆い、独特の地形が水をかき混ぜることなく保っているため赤く見えます。