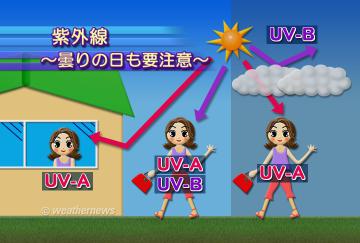5月20日は「世界計量記念日」です。
メートル条約の締結125周年を記念して、2000年から実施されている記念日です。
メートル条約は計量単位の国際的な統一を目標として、1875年に結ばれました。
1960年にはさらに単位の統一を目指そうと、メートル法を拡張した国際単位系(SI)が採択されました。
国際単位は次の7種類の基本量とそれぞれに対する単位を定めています。長さはメートル(m)、質量はキログラム(kg)、時間は秒(s)、電流はアンペア(A)、熱力学温度はケルビン(K)、物質量はモル(mol)、そして光度はカンデラ(cd)が基本単位と決められました。
日常生活になじみのある単位から聞き慣れないものまでありますが、これらは物を計測する上で基礎となる単位であり、国際化が進んでいる現在に必要なものなのです。
お天気豆知識(2025年05月18日(日))


私たちの身の回りに存在する物体のほとんどは、単位をつけて数えます。
身近な食べ物で、ユニークな数え方をするものをいくつか取り上げてみました。
まず、よく耳にするのはイカの「杯」や「本」、食パンの「斤(きん)」です。和菓子のようかんは、大きなかたまりを「棹(さお)」、小さくわけると「切れ」です。高野豆腐は「連」、海苔(のり)は「枚」や「鎚じょう)」、白魚は「ちょぼ」と数えます。
これらの数え方にはそれぞれ由来があり、たとえばイカは軟体動物の貝類に属するため、「貝」を音読みすると「バイ」と読むことから「何バイ」と数えられるようになりました。またようかんは、長細い棒状にして作られる菓子を棹物(さおもの)菓子と呼ぶことから、「棹」で数えます。さらに海苔は複数枚集まると「鍔を使い、10枚で1鎚じょう)です。
このように、ものの単位にはおもしろい数え方や由来があるのです。このほかにどんな数え方があるのか調べてみるのもいいですね。