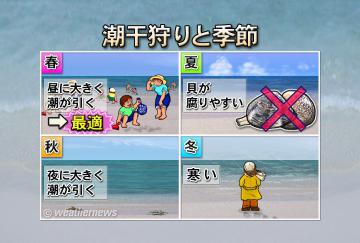ツツジは鮮やかな花の色と空気をきれいにする性質から、街路樹や庭木として親しまれている身近な樹木です。
たくさん種類があるツツジですが、街路樹として植えられることの多いのはヒラドツツジです。
大型の花を咲かせて華やかである一方、乾燥にもある程度耐えられて大気汚染や病虫にも強く、手入れも楽な品種です。また常緑樹なので、季節を問わず空気の浄化作用があります。
野山に自生するツツジで九州の山々に群落をつくって咲くミヤマキリシマは、色の美しさから雲仙(うんぜん)や阿蘇、久住(くじゅう)、霧島など観光地で名物になっています。
ミヤマキリシマは小さな花をぎっしりと並べて咲かせるため、その花つきの良さと色の豊富さから鉢植えとしても人気があります。
そして、高原などに多く自生するレンゲツツジは、花や葉に有毒成分があるものの、その美しさから庭木として植えられることの多いツツジです。中でも黄色の花を付けるものはキレンゲとよばれ、人気があります。
ツツジは野山や都会の道路、庭園とさまざまな場所に春の華やかさを添えているのですね。
お天気豆知識(2025年04月21日(月))


古くから日本人に愛されてきたツツジは各地に名所がありますが、その場所には共通点があります。それは火山地帯が多いということです。
火山地帯の土は酸性であることが多く、ほとんどの植物は弱酸性の土を好むので、あまり生育には適していません。
しかしツツジは酸性の土を好む特徴があり、他の植物が育たない火山地帯でも問題なく育つのです。
ツツジの自生地を見てみると、多くが火山地帯にあります。ここでは他の植物があまり見られず、一面がツツジで覆われていることが多いので開花の時期は見ごたえがあります。
なお、ツツジを家庭で育てる場合、肥料として石灰や鶏糞(けいふん)を使ってしまうと土がアルカリ化してしまい、酸性を好むツツジの生育を悪くするので注意が必要でしょう。