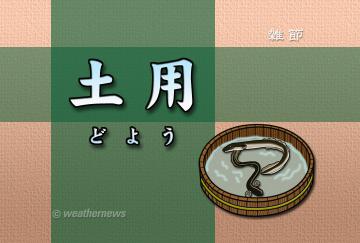アサリはサハリンから日本沿岸、さらにはフィリピンにまで生息している二枚貝です。その名前の由来は、浅いところにすむから、また簡単に「漁(あさ)る貝」など、諸説あるようです。
日本では北海道から九州にかけての沿岸で、ほぼ1年を通してとることができます。アサリは古代から日本人にとってなじみ深い貝のひとつで、多くの貝塚が発見されていることからもそれがわかります。
江戸時代には庶民の人気食として親しまれていて、アサリの煮付けや深川飯(アサリを味噌やネギと炊き込んだご飯)が流行していました。
その人気は現在も変わらず、みそ汁や酒蒸し、クラムチャウダーなど、和洋問わず幅広い料理に使われています。ちなみに、魚屋やスーパーで新鮮なアサリを選ぶコツは、殻の模様が鮮明で、しっかり口を閉じているものを探すことです。
模様がはっきりしていなかったり、足が出ているものは老いたり弱っている場合があります。新鮮なものは味がいいので、上手に選んで、いろいろな料理で味わってみてください。
お天気豆知識(2025年04月11日(金))
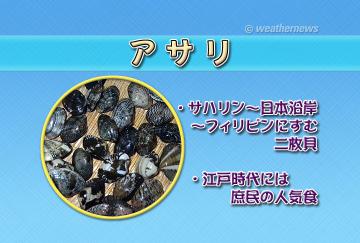

アサリとシジミは魚介類の中でも日本人になじみの深い貝です。アサリのほうがシジミより一回り大きく、両者を見分けるのは簡単ですが、見た目以外にどのような違いがあるのでしょう。
まず、旬が違います。アサリの旬は産卵前の春先と秋口ですが、シジミは「寒シジミ」という言葉があるように、冬が食べごろです。夏の暑さで弱った肝臓には「土用シジミ」がよい、という昔の人の知恵があり、夏も旬といえます。
また、生息地も異なります。アサリは海水にすみ、水深10センチほどの砂底に潜っています。一方、シジミは淡水や汽水の湖や、海と川の水が入り交じったところなどに生息します。
たとえば、本州から九州に生息するマシジミは淡水性、もっとも多く消費されているヤマトシジミは淡水・汽水性です。貝を調理するとき砂抜きをする必要がありますが、アサリは塩水で、シジミは真水につけて砂を吐かせる理由は生息地の違いによるものなのです。
さらに、栄養面の特徴にも違いがあります。アサリは肌の美容に効果があるとされるビタミンAが多く、シジミは骨や歯を丈夫にするカルシウムが特に多く含まれています。
アサリとシジミはどちらも栄養が豊富な貝なので、健康のためにもいろいろな料理にして食べてみてはいかがでしょうか。