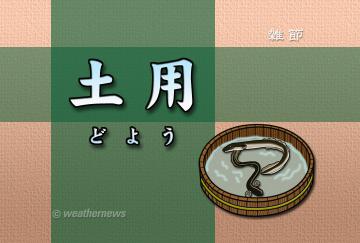セミの鳴き声に真夏を実感する季節が近づいてきました。
セミの鳴き声はいろいろで、暑さに拍車をかけるものもあれば、風情を感じさせるものもあります。
種類によって鳴く時間帯もさまざまです。全国に最も多く生息するアブラゼミは、およそ午前7時から午後8時の間によく鳴きます。ミンミンゼミは、午前7時から午後4時ごろにかけて鳴き、特に午前10時から午後2時にかけて最も盛んに鳴きます。
カナカナカナと鳴くヒグラシは、時期によって若干前後するものの、日の出前の午前4時から5時の間と、日の入り前後の午後6時から8時にかけて鳴くセミです。ニイニイゼミは鳴く時間帯が特に長く、午前4時ごろから鳴きはじめて午後8時ごろまで絶え間なく続きます。
鳴く時間帯が異なる理由は、セミの種類によって好きな気温や明るさがあるためだと考えられています。耳を傾けると時間によってセミの鳴き声が交替していくのに気づくでしょう。
お天気豆知識(2025年07月19日(土))


日本のセミは昼を中心に活動するため、セミの鳴き声は昼間に聞こえるのが普通です。これは、セミには気温や明るさに反応して鳴く習性があるためです。
しかし、セミの鳴き声を深夜に聞いたことはないでしょうか。
熱帯夜などの気温の高い夜、人工の明かりのもとでは、セミが昼と勘違いして、深夜でも鳴くことがあるのだと考えられています。特に、アスファルトやコンクリートに覆われた都市部は、夜間でも比較的気温が高いことが多く、街の明かりもたくさんあります。
街灯のそばにある木などで深夜にセミが鳴くことも多いのです。ふだんから長い時間鳴き続けるニイニイゼミは、街灯があると深夜も鳴いてしまうため、昼夜を問わず何日間も休むことなく鳴き続けることさえあるといいます。
私たちの生活が知らず知らずのうちにセミにも影響しているのかもしれませんね。