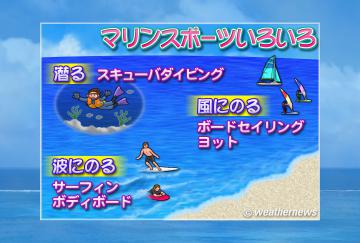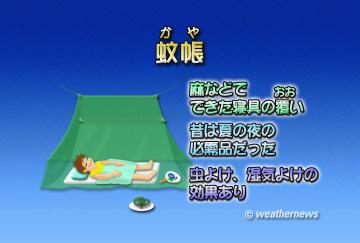多くの所で桜が咲き、入学式の季節を迎えています。初めて通学することになる小学1年生の持ち物は、鉛筆にノート、教科書、どれをとっても真新しいもので、皆さんもうきうきした気分になった当時の記憶が思いだされるのではないでしょうか。
そして、これから毎日背負って通うことになる新しいランドセルも、小学校の6年間をともに過ごしていく大事なかばんといえるでしょう。
ランドセルは、オランダ語で背負い式かばんを意味する「ランセル」からきた言葉です。その歴史は古く、江戸時代末期に西洋式の軍隊制度が導入された際、背中に背負う布製の背のう(はいのう)も同時に輸入されました。
これが日本のランドセルの始まりで、しばらくは軍用に利用されていましたが、明治になって学生の通学にも使われるようになりました。
ランドセルは、両手が自由に使え子供の負担が軽減できるという利点から、小学生用として普及し始めましたが、全国的に広まったのは昭和30年代以降です。
それから現在に至るまで、日本の小学生にとってランドセルは欠かせないものとなっているのです。
お天気豆知識(2025年04月05日(土))


日本の小学生はランドセルを背中に背負って通学しますが、世界の小学生も同様なのでしょうか。やはり国が違うと、通学かばんも様々なようです。
例えば、日本と同じ背負い式のかばんを使用している国には、イギリスやノルウェーがあります。ただ、形は日本のランドセルとは違い、イギリスの場合は「サッシェル」とよばれ日本のものより小さめです。また、おとなり韓国も、革製のランドセルに似たかばんで通学しています。
一方、日本の中学生や高校生が使うことの多い手提げ式のかばんを利用している国にはロシアやインド、ブラジルがあります。ブラジルは全国的に広まっているわけではありませんが、市街地に住む小学生にはこの手提げ式が人気のようです。
また、ショルダータイプの肩かけかばんを愛用している国には中国やシンガポールがあります。ともに「ツーパオ」と呼ばれ、布や皮革(ひかく)でできているのが主流です。
そして、背負い式でも手提げでも併用できるものを使っている国にはドイツやフランス、イタリアなどがあります。このタイプは主にヨーロッパの国々で普及していて、国によって大きさや色、素材などが違います。
フランスは黒か茶色が好まれますが、ドイツの場合はカラフルで男の子は青や茶色、女の子には赤が好まれているようです。
ちなみに、アメリカやカナダなどは、決まった形のランドセルはありません。教科書は学校に置いてあり、手ぶらで登下校するのが普通です。