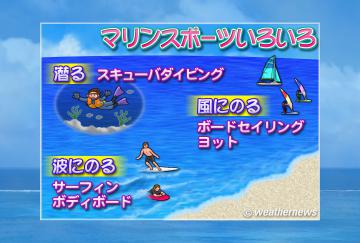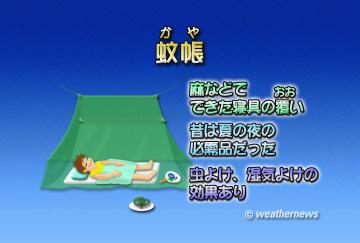春は歓迎会やお花見などでお酒を飲む機会が多い時期です。お酒に含まれるアルコールは中枢神経系に作用するため、多くの人は「酔った」状態になります。
この「酔い」には段階があり、「ほろ酔い期」「めいてい期」「泥酔期」があります。それぞれの段階は血中のアルコール濃度に比例しています。
「ほろ酔い期」は多くの人が上機嫌になったり、判断力が鈍ってきたりしますが、この程度の飲酒ならば、緊張感や不安感を和らげてくれるため、リラックス効果があるとされています。
そしてさらに血中アルコール濃度が上がると「めいてい期」に入ります。この状態になると、千鳥足になったり、怒りっぽくなります。さらに酔いが進むと「泥酔期」となり、意識がはっきりせず、まともに立てない状態になります。
一般的に体重60から70キロの人がビール大ビンを1本飲むと、アルコールが消失するまでに3時間かかるといわれています。
そのため、短時間でたくさんのお酒を飲むと体が処理できずに急性アルコール中毒となることもあるのです。おいしくお酒を飲むためには、「ほろ酔い期」の段階で抑えておくのがいいですね。
大前提として、お酒は20歳になってから。また、飲酒後の運転は絶対にやめましょう。
お天気豆知識(2025年04月04日(金))


4月は歓迎会やお花見などで、お酒を口にすることが多いのではないでしょうか。本来、お酒は楽しむために飲むものです。しかし、一気飲みなどで多量のお酒を飲み、急性アルコール中毒になるケースが毎年報告されています。
無理矢理お酒を飲ませたり、面白半分に飲まないことがもっとも大事ですが、万が一、一緒にお酒を飲んでいた人がまともに立てなくなったり、意識がはっきりしなくなる泥酔状態になったらどうすればいいのでしょう。
その場合、急性アルコール中毒の恐れがあるので症状を確認してください。たたいたり、呼んだりしても反応がなかったり、呼吸が乱れていたり、体温が下がっている場合はすぐに救急車を呼び、その際に飲酒の状況や症状を正確に伝えましょう。
ここで救急車が来るまでにやっておくことがあります。まず衣服を緩めて楽な格好にしてください。そして身体が冷えないよう毛布や上着などで保温します。このとき酔いをさまそうとして水をかけるのはさらに体温が下がるので危険です。
さらにおう吐する場合があるので、吐いた物が逆流して気道を塞がないよう注意し、必要に応じて横向きの体勢を保ちましょう。
無謀な飲み方をすると、どんなにお酒の強い人でも急性アルコール中毒になる恐れがあります。お酒の席では人に一気飲みを強要せず、自分の適量をマイペースで飲むよう心がけましょう。