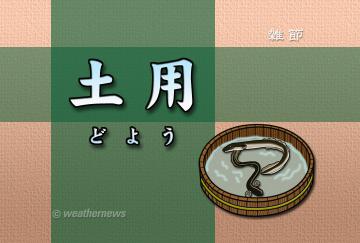春になると、田んぼを一面ピンクに染めるレンゲ畑を見かけることがあります。
最近は近所の田んぼは宅地に変わり、都会ではめっきり見る機会が減ってしまいました。郊外に出かけていくと、田んぼに咲いているレンゲソウを見ることができます。
レンゲソウは、田んぼ、野原、土手、畦(あぜ)などに生える、4月から6月に花が咲く中国原産の植物です。花は赤紫色が主ですが、時折、白色もあります。茎は、根元で枝分かれして地面をはって広がり、地面から上の部分は、10から40センチにも達します。葉は、卵形の薄い小さな葉が10枚前後あります。開花後、黒色のエンドウ豆のようなさやを付け、中には数個の種子ができます。実が熟すると、さやから種をこぼします。
レンゲソウという名は、茎の先に小さなチョウのような形をした花が10個ほど輪状に咲くさまが、亙ハス)の花に似ていることから付けられました。豆科で、ゲンゲ属に属し、ゲンゲとも呼ばれます。また紫雲英(しうんえい)とも呼ばれるのは、赤紫色のレンゲソウの花が一面に咲き乱れている風景を、紫雲が低くたなびいている様子に見立てたものです。紫雲とは、めでたい雲の意味で、英とは、花の意味です。
お天気豆知識(2025年04月02日(水))


なぜレンゲソウは、春の田んぼで多く見られるのでしょうか。それはレンゲソウが豆科の植物であることに理由があるようです。
作物栽培で肥料としてかかせないのが窒素(ちっそ)です。窒素は地球の大気中の80パーセントを占めていて、空気中にはたくさんあります。
この空気中の窒素を地中にもたらしてくれるのが豆科の作物で、正確には豆科作物と共生する根粒(こんりゅう)バクテリアの働きによります。
レンゲソウを根ごとひき抜いてみると、根にジャガイモのイモのような小さなつぶつぶがついています。このつぶつぶが根粒といわれるもので、中にバクテリアが住んでいます。
根粒バクテリアは空気中の窒素を取り入れてレンゲソウに提供します。このため、稲刈りが終わったあとの田んぼに、農家の方がレンゲソウの種をまいて育てるのです。春になって咲いたレンゲソウを田植え前に土と一緒に混ぜておくと天然の窒素肥料として稲の成長のために利用できます。
収穫しないで土に混ぜ、肥料にする植物は緑肥(りょくひ)とよばれ、化学肥料が使われる前にはよく利用されていました。手間はかかりますが、肥料としてレンゲソウをすきこむだけで、無農薬のお米を作ることもできるのです。