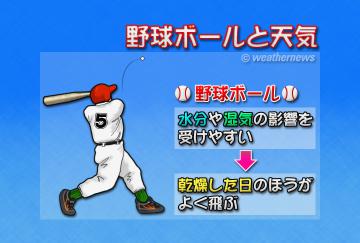3月も終わりとなり、北国でも暖かく感じる日が多くなってきました。冬の間積もっていた雪も春の日ざしとともにとけ出してきましたが、下層は固い氷となっており、また白い雪は光を反射してしまうので意外にとけにくいものです。
また、日中にとけた表面の雪は夜になると再び凍結し、凍ったりとけたりを繰り返すことにより道はぐちゃぐちゃになって歩きにくくなります。
そのため、人通りの多い場所では安全のためにも早く雪や氷をとかして地面を乾かす必要があります。そこで雪の多い地域で行われているのが「雪割り」と呼ばれる作業で、雪国の早春の風物詩となっています。
雪割りは固い氷や雪をスコップやつるはしなどで割り、雪どけを早める作業です。雪割りを行うと、雪や氷が空気に接する面積が増えるためにとけやすくなります。
さらに、白い雪よりも黒っぽい地面の方が熱を吸収するため、この熱が周りの雪や氷がとけるのを助けてくれるのです。
札幌市の場合、雪割りは片側2車線の道路など比較的大きな道路については市が行い、住宅地にある狭い道などは市民の手によって行われています。
割られた氷は道路のわきに集められ、通常1週間から2週間ほどで自然にとけてしまいます。雪割りは雪をとかし早く春を迎えるための知恵なのです。
お天気豆知識(2025年03月30日(日))
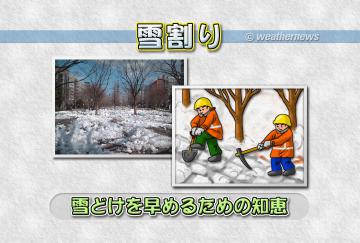

「雪割り」は雪国の春を迎えるための作業ですが、この「雪割り」と同じ名前の植物があるのをご存じですか。その名も「雪割草(ゆきわりそう)」です。
雪割草は名前からも想像がつくように、雪どけ直後の山野に咲く小さい花です。「雪割草」とはその様子から付けられた俗称で、正式にはミスミソウ(三角草)やスハマソウ(洲浜草)という名前をもちます。
ミスミソウは葉の先がとがっているのが特徴で、西日本に分布しています。一方、スハマソウは葉の先が丸く、本州と四国に分布する種類です。ともにキンポウゲ科ミスミソウ属に分類され、花の色は白、淡い青、淡い紫、濃いピンクと様々なものがあります。
ほかにもオオミスミソウ、ケスハマソウと呼ばれるものもあり、山の斜面に自生し、今の時期に小さな花を咲かせます。
これら雪割草は、初心者でも容易に種から育てることができるため、園芸品種としても人気があります。春の訪れを告げる雪割草を育ててみてはいかがでしょうか。