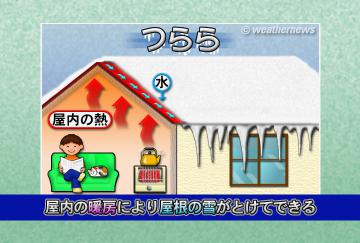今から70年以上前の1952年3月29日は、阿寒湖のマリモが特別天然記念物に指定された日です。
マリモは緑藻類(りょくそうるい)シオグサ科に分類される淡水にすむ藻です。これは大きなひとつの藻に見えますが、実はたくさんの小さな糸状の藻が絡まり合ってできたものなのです。
マリモのきれいな球形は、湖の中を伝わる水の振動が藻を絡ませたり、絡んだ藻が外側に向かって伸びていくことでつくられるといわれています。
マリモは藻が絡みつくことと、絡んだ藻のそれぞれが生長することで大きくなっていきますが、それはとてもゆっくりしたもので、直径6センチメートルくらいの大きさになるのでさえ、150年から200年ほどもかかるといわれています。
中には直径30センチメートルに達するものもあり、そのくらいの大きさになると、まもなく自分の重さに耐えきれなくなって崩れ、分裂します。
ただ分裂してもそれぞれがまた小さな藻の塊として、新しいマリモに生長していきます。マリモは生長と分裂を繰り返しながら、長い年月をかけて増えていくのですね。
お天気豆知識(2025年03月28日(金))


阿寒湖のマリモは特別天然記念物なので、持ち帰ることはできませんが、マリモで有名な阿寒湖や富士山麓の山中湖周辺などでは、おみやげ用に養殖マリモが販売されています。また最近では、ペットショップやフラワーショップでもマリモを見かけることがあります。
マリモは特別天然記念物に指定されるほどの珍しいものなので、養殖マリモを買っても管理が難しそうと思いがちですが、実は意外に簡単です。
容器の大きさやマリモの数にもよりますが、週に一度くらい水をかえるだけで育ってくれます。ただし、もともと寒い所にすむ生き物なので低温には強いものの、暑さには弱く、夏は頻繁に水を替えてあげる必要があります。
また、マリモは光合成をするため十分な日光が必要になりますが、直射日光では強すぎるので、ガラスやレースのカーテンなどを通したやわらかい光を浴びるようにしてください。
ちなみにマリモは金魚などのえさになってしまうので、一緒の水槽には入れないようにしましょう。
こうして上手に育てても、水槽にはマリモを丸くするための水流がなく、養殖物だと藻が生長する際にきれいな球形を保ってくれないこともあるので、水をかえる時に手のひらでやさしく丸め、形を整えてあげて下さい。