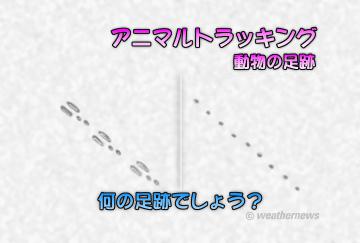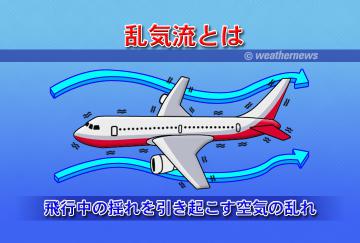日本人にとってタイはおめでたい魚です。日本人とタイの歴史は古く、「万葉集」や「日本書紀」にもたびたび登場し、貝塚にはタイの骨が発見されているほどです。
タイは福を招くためや、お祝い事の際に神仏への祈願や返礼のために用いられていました。ただ外国ではあまり食べることはないようで、お隣中国でも「死者の肉を食らう」といって嫌われ者の魚のようで、タイをこよなく愛するのは、やはり日本人だからなのでしょうか。
さて、日本近海に生息するタイの中でもマダイは日本で一年通しておめでたい席に登場する魚ですが、旬は春です。ちょうど産卵期を迎える前にあたり、もっとも美味しい頃なのです。
これから桜の咲く季節になるとマダイもまた、桜の花の様な美しい紅色になるので、別名「桜鯛(さくらだい)」と呼ばれています。煮付けにしたり、お吸い物にしたり、新鮮なものならお刺身で食べたいものです。
なお、「腐っても鯛」ということわざがありますが、タイのたんぱく質は分解が遅いので、比較的腐りにくい魚といえるようです。
お天気豆知識(2025年03月13日(木))


マダイが「桜鯛」と呼ばれるように美しい紅色になるのはエサに秘密があります。
そもそもマダイは雑食性で何でもたべますが、「エビでタイを釣る」ということわざがあるように、エビなどの甲殻類が大好物です。
このエビの殻にアスタキサンチンという色素が含まれていて、これを食べたマダイは桜色に染まるのです。
しかし、マダイは人と同じように体の表面にメラニン色素を持っています。このため、紫外線を浴びると日焼けをして、体の色が黒くなってしまいます。
やはり紅色に染まった鯛が人気のようで、養殖場では生け簀を沈めたり、覆いをかけるなどして日焼け防止に努めています。