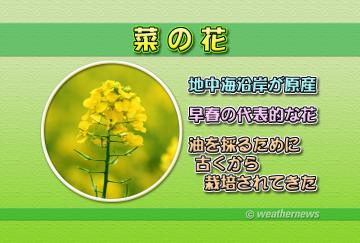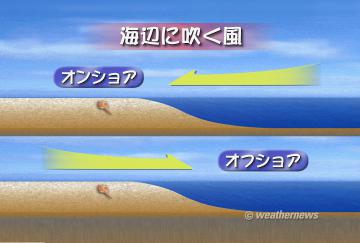一口に冬といっても、例年に増して寒い日が多い年もあれば、冬の期間を通していつもより暖かい年もあります。
平年よりも寒い冬というのは、大陸のシベリア高気圧が発達し、日本の東側に現れる低気圧がいつもより南で発達することが多いときです。
このような年は、日本付近はいわゆる西高東低の冬型の気圧配置が続いて、天気図には等圧線の縦じま模様が頻繁に見られます。
一方、暖冬になるときは、西のシベリア高気圧と東の低気圧の勢力がともに弱く、位置も北に寄っている場合、もしくはシベリア高気圧が勢力を強めて西シベリアから中近東にかけて張り出し、寒波が日本に来なくなる場合です。
このときは春のように移動性高気圧と低気圧が交互に日本付近を通過することが多くなり、暖かい南風がたびたび吹きます。
お天気豆知識(2024年12月05日(木))


ジェット気流は季節によって位置や流れを変えます。
冬、ジェット気流が大きく蛇行して日本上空にまで南下すると、日本が北の冷たい空気に覆われ、寒さが厳しくなります。そのため、その年の冬が寒いのか、暖かいのかは、ジェット気流がどの程度蛇行して日本付近まで南下するのかによって、おおよそ決まってきます。
一般に、ジェット気流が東西方向に強く吹いて、あまり南北に蛇行しない冬は、ジェット気流は日本の北側にとどまることが多く、暖冬になりやすいといわれています。
逆に、ジェット気流が南北に大きく蛇行するときには、日本の冬の寒さは厳しいものになることがあります。
とくに、北極を中心にして北半球を眺めたとき、北アメリカ東部、ヨーロッパ、東アジアの3方向にジェット気流が蛇行する形のときは、平年よりも寒い冬になるといわれています。