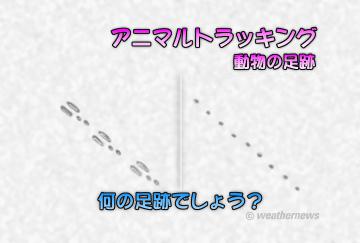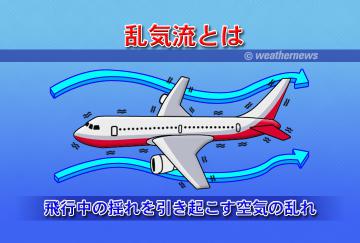今年の夏も猛暑日が続くなど、平年より暑い夏となり、「ヒートアイランド」という言葉をよく耳にしたのではないでしょうか。
都市部の気温が郊外に比べて高温になる現象を「ヒートアイランド現象」と言いますが、この現象は夏だけのものではありません。都市部と郊外との気温差は、一年を通して見ると夏よりも冬の方が大きくなります。
たとえば東京都心では、冬や春先の早朝の気温が郊外に比べて数度高いことが頻繁にあり、ときには10度ほど高いこともあるのです。
高温になっているのは地表面だけではなく、上空にも暖かい空気は広がっていて、ドームのようなかたちをしています。まさに都市の高温部は、熱の島「ヒートアイランド」となっているのです。
ドームの中では都心と郊外との温度差によって風が生じています。高温の都心では上昇気流が発生した後、上空へのぼった空気は郊外に向かって広がりながら冷えて下降し、地上では都市周辺の郊外から都心に向かって風が吹き込むという流れです。
ヒートアイランドの中ではこのような流れのため、外の空気との交換が容易ではありません。そのため、都市部で汚れた空気がたまりやすい構造にもなっているのです。
お天気豆知識(2024年11月27日(水))


郊外に比べて都市の気温が高くなるヒートアイランド現象は、どうして起こるのでしょうか。その主な原因のひとつとして、人工的な熱の排出を挙げることができます。
熱は、冷暖房によるものだけでなく、電気やガス、ガソリンなどの燃料やエネルギーの消費に伴って発生します。
人口の多い都市部では排出される人工熱も膨大で、結果として都市の気温を上げているのです。また、緑地が少ないことも都市を暖まりやすくしている要因のひとつです。
樹木や土の地面が広がっているところは、水分の蒸発が盛んで、そのとき周囲から熱を奪うため、気温を下げる作用が働いています。しかし、コンクリートやアスファルトに覆われている都市部では、この効果もほとんどありません。
高層建築の多い都市部は、風通しが悪いことも冷えにくい環境を生み出しています。高層の建物が風をさえぎるため、郊外の比較的冷えた空気を十分に取り入れて換気することができず、高温の状態を解消できないのです。
このようなさまざまな要因が複雑に絡み合って、都市のヒートアイランド現象を発生させているのです。