これから寒さが増してくるとともに、大根がおいしい時期を迎えます。大根を使った料理にはさまざまなものがありますが、大根を漬け物にしたたくあんもこれからが一番おいしい時期です。
たくあんをつくるときは、腐敗を防いだり味を浸透させやすくするためにまず大根の水分を抜く必要がありますが、これには2つの方法があります。
最も一般的なのは、天日や風にさらして乾燥させる方法です。今では少なくなりましたが、家の軒から大根を縄ですだれ状に吊るしたり、木のやぐらを組み、大根を並べて掛けている風景を見たことがある方もいることでしょう。
天日や風で干してから漬け込んだものは「干したくあん」といい、コリコリとした強い歯ごたえがあります。
もう一つは、日光や風を利用せず、生の大根を塩に漬け込むことで脱水する方法です。塩漬けにして乾燥させてつくられるたくあんは「塩押したくあん」とよばれ、柔らかい食感が特徴です。
これから、たくあんのおいしい時期に、干したくあんと塩押したくあんを食べ比べてみてはいかがでしょうか。
お天気豆知識(2024年11月19日(火))

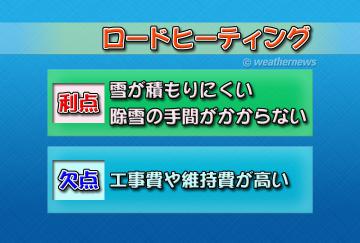
たくあんは長年日本人に好まれてきた漬け物で、地方によって作り方もさまざまです。たとえば、北海道の「早漬たくあん」は、漬け込み期間が数日以内と短いため、漬け物特有のうまみは乏しいものの、ビタミン類の損失が少ないたくあんです。
また、秋田県には「いぶりたくあん」とよばれるいぶして乾燥させるたくあんがあります。雪の多い秋田では大根を外で干すことができないので、天井から大根を吊り下げていろりの火で乾燥させているのです。そのため、たくあんにはいぶすことで生まれた独特の香りがあります。
一方、東京では塩で脱水する「塩押したくあん」が主流で、「東京たくあん」とよばれています。これは大正から昭和にかけてたくあんの出荷量が激増し、製造が間に合わなくなったために考え出されたたくあんで、早ければ漬け込んでから1週間で食べることができます。
反対に、2年以上という長い時間をかけてじっくり漬けるたくあんもあります。長いものは2メートルに達するという愛知県特産の「守口大根」を使った「守口漬」です。塩漬けした後、酒かすに数回漬け込み、最後にみりんかすとみりんに漬けてつくられます。
山口県名産の「寒漬」は大根を塩漬けにし、さらに寒風にさらして干し上げ、醤油につけ込んだものです。寒さの厳しいころに漬けられることからこの名が付いたとされています。
鹿児島県には大きなつぼで漬け込む「山川漬」というたくあんがあります。大根を天日と寒風にさらして乾燥させ、海水を入れたうすに浸してきねでついて柔らかくします。さらに風干ししたあと塩もみし、つぼに密閉して漬け込んでつくられます。つぼを使うことから「つぼ漬け」ともいいます。
一口にたくあんといっても、地域によってそのつくられ方はさまざまで、味や香り、食感にも大きな違いがあるのです。



