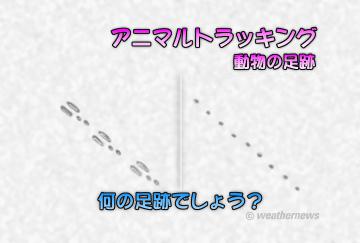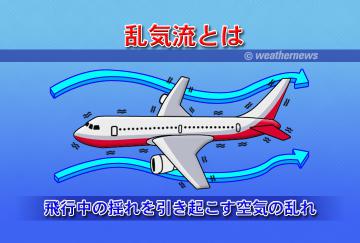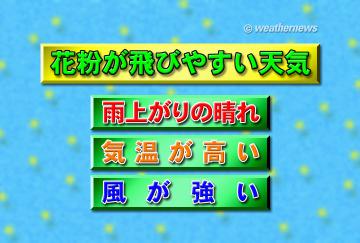近頃は日に日に寒さが増してきて、冬を意識させるような冷たい風が吹く日も多くなってきました。
秋の天気変化は、移動性高気圧と低気圧が交互に日本付近にやってくるのが特徴です。
そして、初冬になるとシベリア大陸から厳しい寒さを持った高気圧が張り出し、北海道の東海上やアリューシャン方面には低気圧があって、しばしば西高東低の冬型の気圧配置が現れます。
天気図には縦じまの模様の等圧線が見られ、日本付近は冬の季節風である北西の風が吹くようになります。
しかし、まだ冬の始まりのころは、冬型の気圧配置も長続きはせず、西にあった移動性高気圧がやがて日本列島を覆い全国的に小春日和となります。
お天気豆知識(2024年11月08日(金))


初冬の気圧配置は、一時的な西高東低の冬型と日本を移動性高気圧が覆うことの繰り返しですが、実際の天気はどのように変化していくのでしょうか。
一時的に冬型が現れて日本列島に北西の冷たい季節風が強く吹きつけるようになると、暖流の流れる日本海によって暖められた空気がひとかたまりの雲をつくり、日本海側に雨をもたらします。
この雨雲のかたまりが断続的にやってくることで、日本海側の地域では時雨になります。一方、太平洋側では、日本海側に雨を降らせた雲が流れ込むことはなく、青空が広がり、冷たい木枯らしが吹きます。
その後、大陸にあった高気圧が日本を広く覆うようになると、木枯らしは止んで全国的に穏やかな小春日和となります。
ちなみに小春日和とは、11月から12月初めごろの暖かな日和のことです。初冬の天気のリズムを把握して、行楽などの計画を立てる際の参考にしてみてはいかがでしょうか。