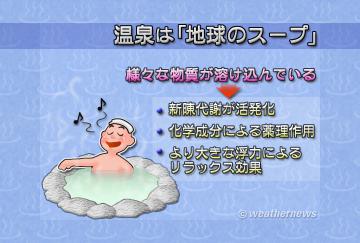11月も終わりに近づき、いくつかのゲレンデはすでにオープンしています。最近では、紅葉を迎えたばかりの時期からでもスキーが楽しめるようになってきました。それを可能にしているのが、「人工降雪久や「人工造雪久です。
人工降雪機は気温の低いときに空中へ水と圧縮した空気を噴射し、空気中で凍らせて雪を降らせる機械です。そのため人工降雪機は気温と湿度の影響を大きく受けます。
気温が低くて湿度が少ないほど質の良い雪になりますが、プラスの気温では湿度が十分に低くないと雪を降らせることはできません。
一方、人工造雪機とはその名の通り、人工的に雪を作って噴射するため、細かく削り出した氷を空気とともに噴出するため、人工造雪機はほとんど天気に左右されません。夏でも雪を積もらせることができ、気温が30度を超えた状態でも雪を降らせることができます。
このような機械の登場によって、天気に大きく左右されてきたスキー場も、人工雪を利用して安定した営業ができるようになっているのです。
お天気豆知識(2025年11月20日(木))


スキーやスノーボードを楽しむときに、ゲレンデの雪質は大変気になるものです。最も好まれる雪質は新雪で、これは密度にすると1立方センチメートルあたり0.03から0.15グラムになります。
新雪が氷点下の状態で1週間ほど経過すると、しまり雪になります。しまり雪は雪の結晶同士がくっつき、粒自体も成長しているため、密度は0.2グラムから0.5グラムに増しています。
また、気温が特に低くて雪の少ない地方では、しもざらめ雪とよばれるものを見ることができます。これは気温が大変低いためにできるもので、外気と比べて暖かい雪の下層から出る水蒸気が表層につくった霜のことです。雪といっても氷に近いものなので、密度は0.25から0.4グラムで、新雪に比べて重さがあります。
そして、比較的気温の下がらない西日本などでは、雪はざらめ雪が主流です。雪が溶けたり凍ったりを繰り返すことでできるこのざらめ雪は、まさに氷でできたざらめのようであり、密度は0.3から0.5グラムです。
しかし、ざらめ雪が主流の西日本などでも、最近は人工造雪機の活躍によってパウダースノーが楽しめるようになっています。