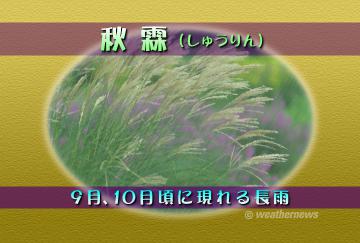秋風が吹くようになると、多くの植物が実りの時期を迎えますが、そんな植物の一つにひょうたんがあります。
ひょうたんはウリ科の一年草で、ユウガオの変種です。そのため、花は夕方に咲き、翌朝にしぼみます。果実は苦みが強いため食用には向きませんが、1週間から2週間ほど水につけて中身を腐らせ、取り除き、乾燥させると、容器として利用することができます。
ひょうたんの多くは中央部分がくびれた独特の形をしているため、縦に切れば水くみに便利なひしゃくになり、横に切ればおわんになります。そのため、土器しかなかった縄文時代には、ひょうたんは無くてはならない生活用品だったのです。
お天気豆知識(2025年09月15日(月))


ひょうたんは人類で最初の容器といわれていて、一説にはそのご発達した陶器も最初は、ひょうたんから作られた容器をまねた形のものだったと考えられています。
ひょうたんはとても軽く、加工や修理がたやすいため、大昔から水やお酒などを入れる容器として重宝されていました。しかし、江戸時代には容器として利用されることも少なくなり、また、プラスチック製品が出回るようになった最近では、ひょうたん自体を目にすることも少なくなってきました。
私達の日常生活からは遠ざかってしまいましたが、ひょうたんには容器以外にも飾り物や楽器としての役割があり、それは現代でも続いています。例えば、その空洞を共鳴体にして、太鼓や弦楽器に加工され、西アフリカではバラフォンという木琴の一種にも利用されています。また、本来マラカスの実で作るマラカスも、同じウリ科のひょうたんに種などを入れてつくることができます。
時代とともに用途は変わっても、大昔からの私達とひょうたんとのつきあいはまだまだ続いているのです。