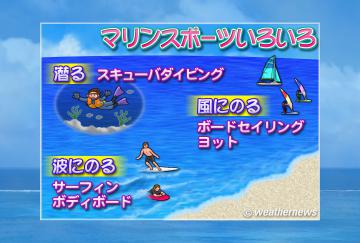西日本や東日本では梅の季節となっています。早春に花を咲かせる梅は古くから日本の人々に愛され、万葉集や古今集などにもたくさんの梅の歌が詠まれてきました。
その中でも菅原道真は梅をこよなく愛したといわれています。道真公の歌に、「東風(こち)吹かば匂ひおこせよ梅の花あるじなしとて春な忘れそ」というものがあります。
この歌は道真公が左遷され、大宰府へと出発するときに、京の紅梅殿(こうばいでん)の梅に名残を惜しんで詠んだ歌で、東風が吹いたときは、その匂いを京から太宰府まで届けておくれという意味です。
主人を失った白梅は、主人の後を追って、たった一晩で太宰府へと飛んでいったと言われています。
この梅の木は現在も福岡県の太宰府天満宮にあり、「飛梅(とびうめ)」と呼ばれています。週末を利用してこの伝説の梅を見に、一度足を運んでみるのも良いものですね。
お天気豆知識(2025年02月19日(水))


梅は300種以上の種類があり、分類するのは大変です。
大きくは梅の実をつけるものを「実梅(みうめ)」、花を観賞するものを「花梅(はなうめ)」といったり、花の色で白梅、紅梅といったりします。しかし、花の色に限ってみても種類によって色味や変化などが微妙に違い、その特徴によって以下のように表現されます。
花びらにつやのある明るい紅色のものは「本紅」、また、つぼみのうちはピンク色をしているが、開花すると白に変わるものを「移白(うつりじろ)」と言います。反対につぼみのうちは白い色をしているが、開花すると紅色になるものは「移紅(うつりべに)」です。
そのほか、花弁の周辺が縁取りしたように紅くなっており、芯の部分が淡い色になるものを「口紅」といいます。その他にも絞り染めになる「絞り」や、花弁の裏が紅色で表面が淡色の「裏紅」など、さまざまなものがあります。
梅の花を観賞する時は、花の色にも注目してみるといっそう楽しめるかもしれませんね。