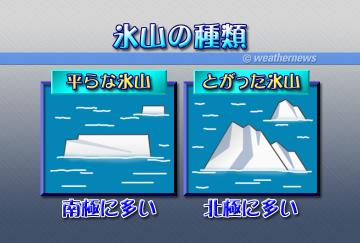シリウスは月や太陽・惑星を除いた星(恒星)の中で最も明るい星として知られ、明るい星が多い冬の夜空でもひときわ目立つ存在です。
そしてその次に明るいのが「カノープス」で、これも冬に姿を現します。カノープスはトロイ戦争に参加したギリシャの水先案内人の名に由来し、「りゅうこつ座」という星座に属しています。この星や星座の名前があまり知られていないのは、日本で見ることが難しいからでしょう。
カノープスは地平線近くの真南の低い空に現れます。また、お隣りの中国でもその存在が知られています。洛陽や西安においては「南極老人星」と呼ばれ、この星が明るく輝いて見えると、天下泰平、国家安泰の印として喜ばれたといわれます。
また、大気の影響で赤く輝いて見えることから、酒好きでいつも赤い顔をした七福神の一人、寿老人(じゅろうじん)に見立て、この星を見つけると長生きできるともされました。
このカノープスを見つけるには、まず全天で最も明るいおおいぬ座のシリウスを探しましょう。そして、そのまま視線を下に移せば、地平線に近い所に明るい星を見つけることができます。なお、カノープスを観察できる時期は一年で最も寒いころです。防寒対策をしっかりして、風邪をひかないように観察しましょう。
お天気豆知識(2025年01月24日(金))


平和や長生きの象徴とされた星「カノープス」は、残念ながら日本全国で見られるわけではありません。
カノープスは、南天の低い位置に輝くため、南の地域ほど見やすく北に行くほど水平線に近づきます。見ることができるのは、北緯37度付近までで、だいたい福島県のいわき市あたりが北限にあたります。
しかし、カノープスが見える北緯37度以南の地域でも、カノープスが南の空に姿を現す時間はとても短く、観察するには、出現する時間帯を把握しておく必要があります。
今の時期(1月下旬ころ)、関東から中部、近畿地方にかけては22時ころに見ることができます。
中国や四国、九州地方であれば22時30分ころになります。南に水平線が見渡せるような、開けた所を選ぶとよいでしょう。