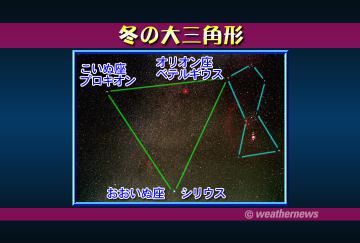12月、夜空に輝く星座に「おひつじ座」があります。おひつじ座は星占いでいつも最初に紹介される星座ですが、それには理由があります。
星占いに出てくる星座は「黄道12星座」と呼ばれていて、太陽の通り道である「黄道」が通る12個の星座のことです。そしてその順番の基準となっているのは、黄道が「天の赤道」を南から北へ横切る地点である「春分点」です。つまり、その春分点が昔はおひつじ座にあり、そのときの名残でいまだにおひつじ座から始まっているのです。なお、現在は春分点が隣の「うお座」に移動しています。
おひつじ座で1番明るい星は「ハマル」という名の2等星です。ちょうど羊の頭部にあたることから、そのまま「ひつじの頭」という意味です。
そして次に明るい星が隣にある「シェラタン」で、「合図」の意味を持つ名前です。今から2000年ほど前のギリシア時代には、この星の近くに太陽がくる時が春分で、その当時の年初のしるしだったことにちなんでいるといわれています。
ギリシア神話では、この羊は、テッサリアという国の王子と王女が殺されそうになったときに彼らを助けた、金色の毛をもつ空飛ぶ羊とされています。また「アルゴ遠征隊」という壮大なストーリーでは、この羊はアルゴ遠征隊が求める金色の毛皮としても登場しています。
お天気豆知識(2024年12月01日(日))


ペルセウス座は、毎年お盆にピークを迎える「ペルセウス座流星群」でご存知の方も多いのではないでしょうか。流星群が活動する8月は夜遅くに北東の空に上がってきますが、今の時期は、宵のうちにはすでに北東の空高くに見ることができます。場所は「カシオペヤ座」の右隣にあたります。
神話によると、ペルセウスはギリシアの最高神ゼウスとアルゴスという国の王女との間に生まれた子供です。メドゥーサという、髪の毛はすべて生きている蛇、歯はライオンの牙よりも鋭く、その顔をまともに見るとたちどころに石に変わってしまう、恐ろしい妖怪の首を取った勇者がペルセウスです。
星座絵の勇者ペルセウスが持つメドゥーサの首の額には、「悪魔の星」という意味をもった「アルゴル」という星が対応しています。このアルゴルは2日と21時間ほどの周期で規則正しく明るさが変わる、変光星と呼ばれる星です。
明るさが変わる原因は、一つの星に見えるアルゴルが、実は二つの星が回り合っているものだからです。地球から見て片方の星がもう片方を隠すとき、暗くなるのです。
もうひとつ注目したいのが、ふり上げた剣の付け根あたりに見える「二重星団」です。二重星団は二つの星団がくっついて見えるもので、これは肉眼より双眼鏡で見ることをお勧めします。