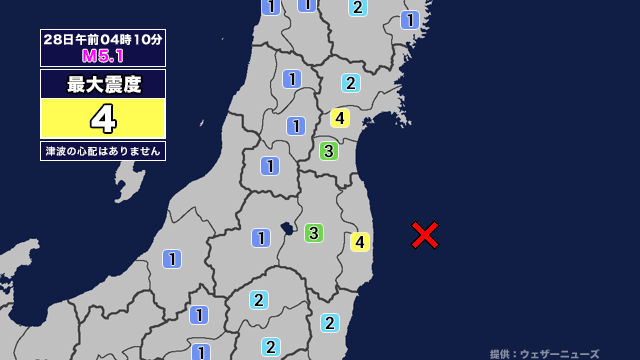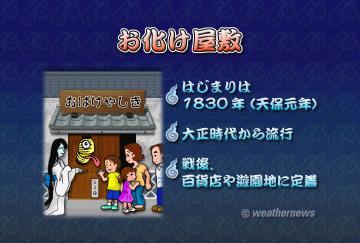お化け屋敷
毎年夏になると、納涼特集として雑誌やテレビなどではお化け屋敷が取り上げられますね。夏の風物詩、お化け屋敷のはじまりは、1830年(天保元年)の江戸時代にさかのぼります。ある医者が、壁から天井まで妖怪(ようかい)の絵を描き、一つ目小僧などの人形を飾り付けた小屋を自宅の庭に作りました。これが評判となり、多くの見物人が集まったのがはじまりとされています。大正時代になるとお化け屋敷を博覧会に特設することが流行し、納涼イベントとして定着しました。人形のおどろおどろしさと光と音の演出によって観客を驚かし楽しませ、スリルとユーモアのあるイベントとして人気を呼びました。昭和に入り戦後になると、お化け屋敷は百貨店や遊園地の催し物として定着し、現在の様な姿となったのです。およそ200年前の人々も、お化け屋敷に出かけていたというのは意外ですね。