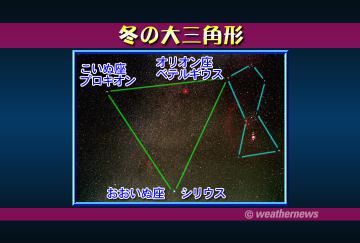秋は周期的に高気圧に覆われて穏やかな晴れの日がやってきます。昼は過ごしやすいのですが、夜間は放射冷却現象が強まって地面付近の空気が冷やされ、霧が発生しやすくなります。
とくに盆地などでは顕著に現れ、愛媛県の大洲盆地(おおずぼんち)では、たいへんめずらしい霧の現象を見ることができます。
大洲盆地にできた霧が肱川(ひじかわ)沿いを下り、強風とともに瀬戸内海沿岸の大洲市長浜(おおずしながはま)まで流れ出て、時には瀬戸内海の数キロ沖合までを一続きに覆うことがあるのです。
この霧をともなった風は「肱川あらし」と呼ばれています。例年、11月ごろから3月ごろにかけて見られる現象で、12月に最も頻繁に現れます。肱川あらしは非常に冷たい風で、肱川河口の長浜あたりで強風となって瞬間的に風速20メートルに達することもあります。
ただ、肱川あらしが吹き荒れるのは朝だけで、午前中のうちに風も収まって霧も消え、昼からは穏やかな晴天になります。高気圧に覆われて晴れそうな日に訪れてみれば、壮大な霧を見ることができるかもしれませんね。
お天気豆知識(2024年10月31日(木))


秋から冬にかけて、愛媛県を流れる肱川(ひじかわ)では、「肱川あらし」と呼ばれる霧をともなった強風が吹くことがあります。
雲や風がない夜間は、放射冷却現象が顕著に現れて、上流の大洲盆地では強く冷え込み、霧が発生します。それに比べて海は暖かく、海上の空気も暖かくて軽いため、盆地で冷やされて重くなった空気は標高の低い肱川河口に向かって流れ出します。
盆地から流れ出た霧は、低地へ行くに従って暖められ徐々に消えていきますが、川や海が上からやってくる空気にくらべて暖かいため、その水面からは湯気のように霧が立ち上ります。
こうして川や海から霧が発生し続けると、大洲盆地から瀬戸内海まで続く霧の帯ができます。また、上流から下ってくる冷たい空気の流れは、河口付近のV字型の地形によって狭められて勢いを増し、強風となります。
その結果、霧と冷たい強風の肱川あらしが発生するのです。肱川あらしは、気象と地形とが複雑に絡み合った神秘的で壮大な現象といえるでしょう。